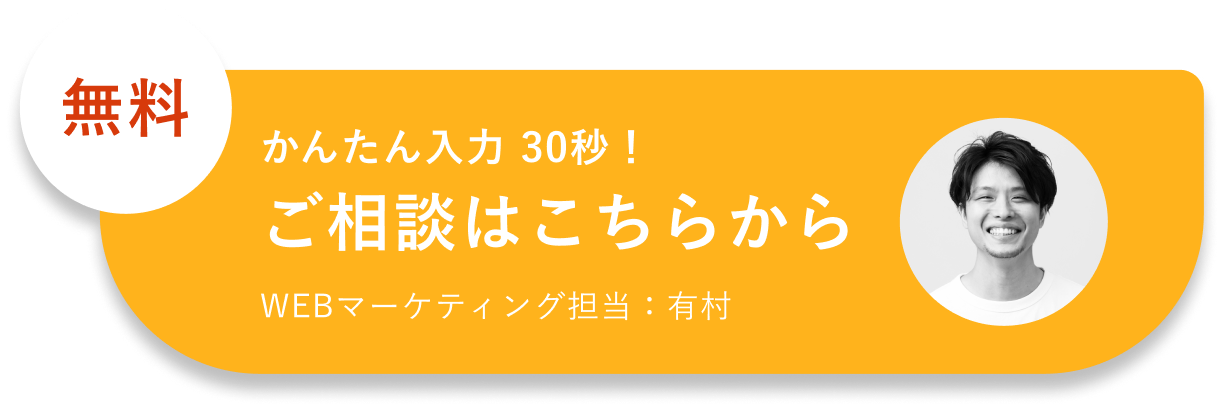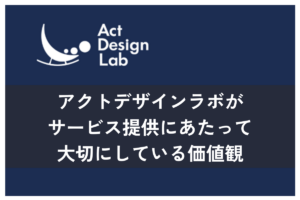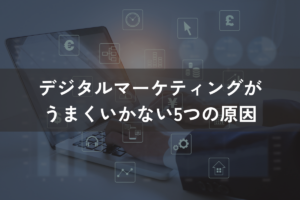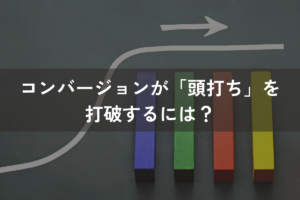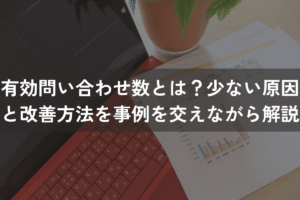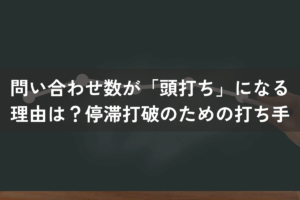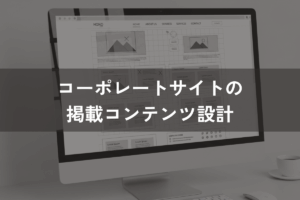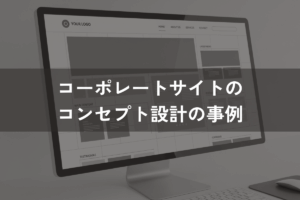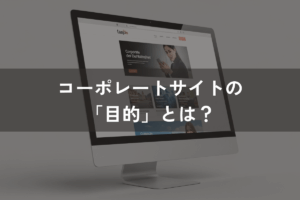サイト改善とは、Webサイトの目的や目標に合わせた修正を施すことで、効果の出せるサイトにしていくことです。
サイトを制作しても思ったような効果が出ないということは良くあります。効果が出ない原因を探索し、細かい改善を繰り返していくことが重要です。今回は、サイト改善の目的・具体策・手順・成功のコツを徹底解説します。
「サイト改善に取り組みたいけど、何から始めればよいかわからない」「サイト改善って具体的にどんな方法があるのか知りたい」「サイト改善で成功した事例を参考にしたい」このようなお悩みをお持ちの方は必読です。2つの成功事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
サイト改善の4つの目的
ゴールを明確にすることで、サイト改善を効率よく進めることができます。サイト改善に取り組む目的は、Webサイトの目的や目標によってさまざまですが、主なものとして次の4つが挙げられます。
- CVRの改善
- CTAの改善
- サイト導線の改善
- SEO対策の改善
それぞれについて解説するので、自社サイトの課題と照らし合わせながら確認してください。
1. CVRの改善
CVRはコンバージョン率のことで、サイトに訪れたユーザーのうち、特定のアクション(コンバージョン)に至った人の割合を指します。コンバージョンはサイトの目的によってさまざまで、購入やお問い合わせ、資料請求などが挙げられます。
CVRの改善は、売上拡大など利益に直結するため、サイトの収益性向上が期待できます。サイト改善の中でも優先度は高いといえるでしょう。
2. CTAの改善
CTA(Call To Action)は「行動喚起」のことで、主にユーザーがコンバージョンに至るために押すボタンのことを指します。CTAを工夫することで、CVRが大きく伸びることもあります。
また、CTAの改善は、ユーザー側にもメリットがあります。CTAがわかりやすいと、ページ上で迷わずスムーズに行動できるため、ユーザーはストレスを感じることがなくなります。企業・ブランドに対するイメージやロイヤリティ向上も期待できるでしょう。
3. サイト導線の改善
サイト導線の改善とは、サイトを訪れたユーザーが見たい情報や商品にスムーズにアクセスできるようにルートを整備することを指します。サイト導線を改善することで、ユーザビリティが向上し、ユーザーの満足度を高めることができます。また、良い利用体験をきっかけにリピートも期待できるでしょう。
4. SEO対策の改善
SEO(Search Engine Optimization)は「検索エンジン最適化」のことで、自社サイトを検索結果の上位に表示させることを指します。検索エンジンに評価されるようサイトの構造やコンテンツを最適化することで、上位表示が狙えます。
SEO対策を改善して検索順位を上げることで、集客力が高まります。また、多くのユーザーの目に留まることで認知拡大につながることもメリットです。
目的別に紹介|サイト改善の具体策
「サイト改善に取り組む目的は理解できたけれど、具体的にどこを改善すれば良いかわからない」という方もいるのではないでしょうか?改善策はさまざまありますが、ここでは主なものを紹介します。
ここでは目的別に紹介しますが、実際は改善策と目的は一対一対応ではなく、一つの改善策を実施することで、さまざまな効果が期待できます。実際に改善を進める際は、効果を最大化できるよう、複数の施策を組み合わせることが大切です。
- CVR改善のための施策
- CTA改善のための施策
- サイト導線改善のための施策
- SEO対策改善のための施策
1. CVR改善のための施策
CVR改善には、コンバージョンにつながるページのコンテンツと、コンバージョンの一歩手前にあたるエントリーフォームを見直すことが有効です。
- コンテンツの数と表示順を見直す
- エントリーフォームを最適化する
コンテンツの数と表示順を見直す
CVRを伸ばすには、ユーザーニーズにマッチした十分な量のコンテンツを、正しい順で並べることが重要です。コンテンツが揃っていても、表示順がユーザーのニーズとマッチしていないことがよくあります。
たとえば、ダイエット食品のECサイトでは、ユーザーは「本当に効果がある?」と思いながらページを読み進めていくと想定されます。にもかかわらず、体験談がページ下部に配置されていたら、体験談にたどり着くまでに離脱してしまうでしょう。
コンテンツを見直す時は、ページを訪れたユーザーになりきって「どんな情報が欲しいか」「どこにその情報があれば嬉しいか」を想像しましょう。
エントリーフォームを最適化する
エントリーフォームは、コンバージョンの一歩手前の段階です。ここでユーザーを逃してしまうのは非常にもったいないので、エントリーフォームに改善すべきポイントがないか必ず確認しましょう。次のポイントを参考にしてみてください。
- 項目数は最低限にする
- 必須項目に「必須」と表示する
- 入力例を入れる
- 住所は郵便番号から自動入力できるようにする
- エラー表示は訂正箇所がひと目で分かるようにする
- 離脱につながる不要なリンクやバナーは入れない
- スクロールが少なくてすむよう縦幅をできるだけ短くする
2. CTA改善のための施策
CTA改善には、CTAの数と表示位置、デザインを見直すことが効果的です。
- CTAの数と表示位置を見直す
- CTAのデザインを変更する
CTAの数と表示位置を見直す
CTAの数と表示位置は、クリック率に大きくかかわります。ユーザーの視線やスクロールの動きを想定しながら検討することが重要です。ヒートマップツールも必要に応じて活用しましょう。
CTAは、ユーザーが購入やお問い合わせなどの行動を取ると想定される箇所に複数設置すると良いですが、多すぎるとページが見づらくなるため注意が必要です。
CTAのデザインを変更する
デザインを工夫することで、コンバージョンのハードルを下げることができます。
ボタンの文言は、「購入する」「お申込みはこちら」など端的でわかりやすい文言にしましょう。ボタンの上に、「先着○○名様限定」「今なら○○プレゼント」などのクリックを促すような一文を入れることも効果的です。
ボタンの色や形は、サイトのデザインやユーザー層にマッチするように工夫しましょう。ボタンの角が丸角か四角かによってもユーザーに与える印象は異なります。
3. サイト導線改善のための施策
サイト導線改善には、サイト内の案内役となるナビゲーションメニューと、ページとページを繋ぐバナーの見直しが効果的です。
- ナビゲーションメニューを最適化する
- バナーの数と表示位置を見直す
ナビゲーションメニューを最適化する
ナビゲーションメニューとは、ページ上部やサイドバーに表示されるリンクの集合のことです。ユーザーが知りたい情報にスムーズにアクセスできるようにする役割があります。
ナビゲーションメニューの項目は、ユーザーにとって優先度が高いと思われるものに絞って、簡潔でわかりやすいラベルを付けることが重要です。
バナーの数と表示位置を見直す
見せたいページに誘導するためにバナーは非常に有効ですが、過度なバナーの配置はユーザーにストレスを与えてしまいかねません。バナーが多すぎて見づらいページになっていたり、ポップアップバナーが邪魔になったりしていないでしょうか?
ユーザー視点に立って、必要な場所に必要な数だけ設置することを意識しましょう。
4. SEO対策改善のための施策
SEO対策改善には、検索エンジンからの評価を高められるよう、サイト構造やタグ、コンテンツの見直しが有効です。
- サイト構造・タグを最適化する
- 検索ニーズにマッチしたコンテンツを追加する
サイト構造・タグを最適化する
検索エンジンから評価されるには、検索エンジンの巡回を促し、正しく情報を読み取ってもらうことが重要です。
サイト内を巡回しやすくするためには、サイトマップの作成や内部リンクを最適化することが有効です。また、正しく情報を読み取ってもらうために、タイトルや見出しタグを整えましょう。
その他にもさまざまな改善ポイントがあるので、できるものから順に取り組むことで効果が期待できます。
検索ニーズにマッチしたコンテンツを追加する
検索エンジンからの評価を高めるには、コンテンツの質も重要な要素です。ユーザーが検索した意図を汲み取り、ユーザーの知りたい情報を盛り込んだコンテンツを用意しましょう。
コンテンツを追加しても結果はすぐに出ないことが多いですが、根気強く取り組むことが大切です。新規コンテンツを追加するだけでなく、公開したコンテンツのメンテナンスもあわせて取り組みましょう。
アクトデザインラボが実施したサイト改善事例
当社アクトデザインラボ株式会社では、あらゆる業種や業界の企業様のWebマーケティングを支援しています。当社の支援によってサイト改善に成功した事例を2つ紹介するので、参考にしてみてください。
事例1:ペット系メディア業界A社様
| 課題 | 流入数は十分獲得できていたが、回遊導線を作り切れていなかった |
| 目標 | 回遊率向上 |
| 解決策 | ①サイト構造の整理とカテゴリの再編 ②伝えるべき情報を精査したうえでクリエイティブを変更 |
ペット系メディアのA社様では、サイトへの流入数は十分に獲得できていたものの、回遊導線を作り切れていないことが課題でした。そこで、回遊率向上を目標に改善策を実施しました。
どこから流入しても、サイト内のどこにどんなコンテンツがあるのかを見渡しやすくするために、サイト構造を整理し、カテゴリの再編を行いました。具体的には、サイト全体のナビゲーションを一新し、多くのユーザーに「目に留まりやすく」「邪魔にならず」「わかりやすい」UIの方針を打ち出して改修を行いました。
また、ユーザーのニーズや当メディアの強みを意識しながら、サイト内で伝えるべき情報を精査し、クリエイティブの変更を行いました。
当メディアの利点がユーザーに伝わりやすい構造にしたことで、「回遊率」「再訪率」の向上だけでなく、ペットに関する困りごとがあったときに想起してもらいやすい状態を作るための土台作りができたという点でも成果を感じていただけました。
事例2:中古品買取業界B社様
| 課題 | 競合の台頭により利益率が低下していた |
| 目標 | 成約率と利益額の向上 |
| 解決策 | ①質の高い問合せが獲得できる都市部以外のエリアへの分散投資 ②サイト内での買取地域の見せ方などの修正 |
中古品買取業界のB社様は、競合の台頭により、利益率が低下していることが課題でした。そこで、量的に戦うのではなく、「成約率」と「利益額」の向上を目標に定め、改善策を実施しました。
都市部での競争が激化していることに着目して、数はそれほど多くないものの、質の高い(成約率、利益額の高い)問合せが獲得できるエリアを探し、分散的に戦っていく方針を打ち出しました。都市部以外の地域でも積極的に買取を行っていることをユーザーにわかりやすく伝えるべく、サイト内の直近の買取地域のコンテンツを目立たせるなどの工夫をしました。
手間のかかる方針をあえて取ったことで、競合が効率性の観点から手を出しにくい空白の市場を発見することに成功し、サイト改善にもつなげることができました。
サイト改善の6つのステップ
サイト改善でよくある失敗として、分析や仮説立てが不十分なまま改善策を実施してしまうことがあります。改善策は一度実施して終わりではなく、改善を繰り返しながら最適化を図っていきます。そのためには、仮説と検証が非常に重要です。
ここでは、サイト改善に取り組む際の手順を6つのステップで紹介します。ぜひ手順に沿って取り組んでみてください。
- サイトの目的を明確にする
- サイトの現状を分析する
- 分析結果をもとに課題を抽出する
- 課題を解決する改善策を検討する
- 改善策に優先順位をつけ実行する
- 効果検証をしてPDCAを回す
ステップ1:サイトの目的を明確にする
まずは、サイトの目的を明確にしましょう。サイトの目的が明確になっていないと、ステップ②以降の分析や課題の抽出、改善策の選定をする際、どこを見るべきか、何を優先すべきかがわからなくなってしまい、効果が出づらくなってしまいます。
サイトの目的の例として次のようなものが挙げられます。改めて自社サイトの目的を確認してください。
- 認知度の向上
- 顧客リストの獲得
- 売上の拡大
- ブランディング
- カスタマーサポート
- 人材の獲得
ステップ2:サイトの現状を分析する
次に、解析ツールを活用してサイトの現状を分析します。サイトの目的によって重視すべき指標は異なりますが、主に見るべき指標は次のとおりです。
- 閲覧数
- 滞在時間
- 直帰率
- 離脱率
- ユーザー行動(離脱箇所・スクロール状況など)
- 流入経路
- 流入キーワード
- CVR
- ユーザー属性
- 使用デバイス
ステップ3:分析結果をもとに課題を抽出する
課題の抽出は、ステップ②で分析したデータに基づいて行うことが非常に重要です。感覚的に、「○○に課題がありそう」と決めつけてしまうことは避けましょう。
また、ステップ①で整理した目的を意識することも大切です。「目的を達成するためにはどこを改善すればよいか」という視点でデータを見るようにしましょう。
ステップ4:課題を解決する改善策を検討する
具体的な改善策を検討していきます。一つの課題に対して、まずは考えられるだけ改善策を挙げてみましょう。たとえば、ECサイトで商品ページの離脱率が高い場合、次のように複数の改善策が考えられます。
- CTAの改善(数・表示位置・デザイン)
- コンテンツを追加する
- チャットボットを導入する
- ページデザインを見直す
- ページの表示速度を上げる
必要性や期待できる効果の大きさはさまざまですが、まずは考えられる施策を洗い出してみることが大切です。
ステップ5:改善策に優先順位をつけ実行する
検討した改善策は、優先順位をつけて、目的に対する効果が高そうなものから着手していきます。改善策は、できれば一つずつ実施することをおすすめします。
同時に複数実施してしまうと、効果が出てもどの施策の効果なのかわからなくなってしまうためです。優先順位に悩んだ時は深く考えすぎず、先に準備ができそうなものや実装が簡単なものからどんどん実施していくようにしましょう。
ステップ6:効果検証をしてPDCAを回す
改善策を実行して、ある程度データが蓄積したタイミングで効果検証をします。効果が出た場合は継続し、効果が出ていない場合は、原因を探索し、軌道修正をしましょう。そして、また効果検証をします。
サイト改善は、一度実施して終わりではなく、効果検証と修正を繰り返しながら継続して実施することで徐々に最適化が図られます。
サイト改善を成功に導く3つのチェックポイント
続いて、サイト改善に取り組む際、意識すると良い3つのポイントを解説します。PDCAを回すなかで、時々立ち止まって次のポイントをおさえられているか確認してみましょう。
- ターゲットが明確になっているか
- ユーザー視点を意識できているか
- 競合サイトに対して優位性があるか
1. ターゲットが明確になっているか
効果的なコンテンツやデザインは、ターゲットの性別や年齢、興味関心によって異なるため、ターゲットが曖昧なまま進めてしまうと期待する効果が得られません。
ターゲットを明確にした後は、チームメンバーや関係者の共通認識にするようにしましょう。コンテンツやデザインの方向性を決定する際、スムーズに進められます。
また、より詳細なターゲット像が必要な場合は、一度ペルソナを作り込むことも効果的です。必要に応じて作成してみてください。
2. ユーザー視点を意識できているか
サイト改善に取り組む際は、ユーザー視点を常に意識してください。ユーザー視点が欠けてしまうと、ユーザーがストレスを感じて離脱しやすくなるだけでなく、企業やブランドに対するイメージダウンにもつながりかねません。
次のポイントを意識すると良いでしょう。
- ユーザーが迷わないサイト導線を引けているか
- ユーザーにとってわかりづらい表現はないか
- ユーザーニーズにマッチしていない不要なコンテンツはないか
- モバイル表示で見づらい箇所はないか
3. 競合サイトに対して優位性があるか
ユーザーは自社サイトだけを訪問しているわけではなく、多くの場合複数サイトを比較しています。自社サイトをチェックする際は、競合サイトに対して優位性があるかという視点を持つことが非常に重要です。
サイト担当者は、競合サイトを定期的に確認する習慣をつけるとよいでしょう。自社サイト改善の参考になるコンテンツやアイディアが見つかることもよくあります。
サイト改善に役立つツール
ツールを活用することで、感覚に頼ることなくデータに基づいた改善が可能になります。改善策を実施した後も定期的にデータを確認する習慣をつけるようにしましょう。
最後に、サイト改善に役立つツールを5種類紹介します。
- Google アナリティクス
- Google Search Console
- ヒートマップツール
- ABテストツール
- EFOツール
Google アナリティクス
Google アナリティクスは、Googleが提供する無料のアクセス解析ツールです。サイトを訪れたユーザーの属性や流入経路だけでなく、サイト内での行動データやコンバージョンの詳細を確認できます。
Googleアカウントを作成して解析したいWebサイトを登録し、トラッキングコードをWebサイトに設定すれば誰でも使えるので、必ず活用しましょう。
Google Search Console
Google Search Consoleは、Googleが提供する無料の検索解析ツールで、自社サイトの検索パフォーマンスを確認できます。
自社サイトがGoogleにおける検索結果に表示された回数やユーザーが検索したキーワード等を分析できるため、SEO対策のために活用しましょう。
ヒートマップツール
ヒートマップツールは、サイト上でのユーザーの行動を、サーモグラフィのように色と濃淡で可視化してくれるツールです。ヒートマップツールを使うことで、ユーザーのクリック箇所やスクロール状況、滞在時間などを把握できます。
ユーザーの離脱ポイントを探る際に役立つため、滞在時間が伸びない、CTAのクリックにつながらないという場合に活用してみましょう。
ABテストツール
ページデザインやCTAデザイン等、複数パターンで比較検証する場合は、ABテストツールを使うことで、Aパターン・Bパターンのページを表示するユーザーをランダムに振り分け、成果を比較できます。テスト結果の管理もしやすくなるので、ABテストを実施する際は活用しましょう。
EFOツール
EFOとは「エントリーフォーム最適化」のことで、ツールの主な機能はフォームの入力支援です。ツールによっては、離脱ポイントやCVRの状況も分析できるので、ツールを導入することで、ABテストではわからない詳細な改善ポイントを把握できるようになります。
まとめ
サイト改善は、すぐに効果が出ることは稀で、継続して改善を繰り返すことで徐々に最適化がはかられます。やみくもに次々と改善を繰り返すのではなく、現状分析をしたうえで仮説検証を繰り返すことを意識しましょう。
改善策は今回紹介した以外にもさまざまあります。紹介した事例も参考に、自社サイトに合った施策を検討してみましょう。
Webを通じて自社の売上を増やしたいとお考えであれば、Web領域全般を任せられる専門家に相談することが一番です。当社アクトデザインラボでは、クライアントと深くコミュニケーションを取りながら本質的な課題を見つけ出し、最適な解を提案します。
「サイト改善に取り組んだものの成果が上がらない」「時間と労力だけが無駄になってしまった」そういった事態に陥らないためにも、ぜひ一度当社にお気軽にお問い合わせください。