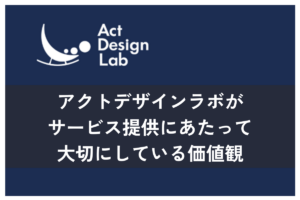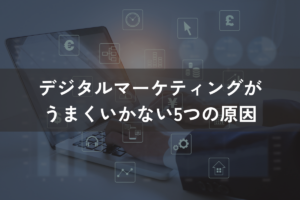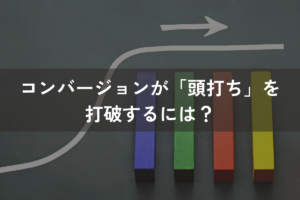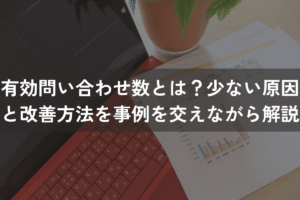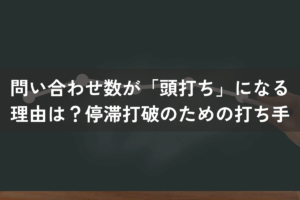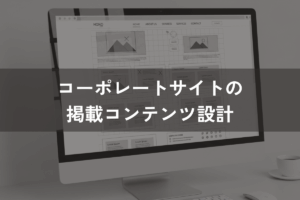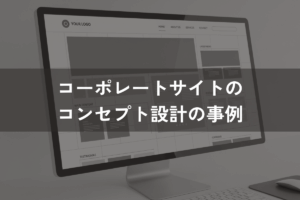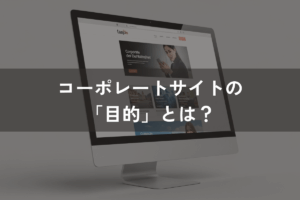BtoB企業にとって、WebサイトからのCVR(コンバージョン率)を高めることは、リードの獲得数を増やし、事業を成長させるための最も重要な取り組みの一つです。にもかかわらず、「流入はあるのにコンバージョンに至らない」「何を改善すれば良いかわからない」「打ち手が見つからず立ち止まっている」といった課題を抱えている企業は少なくありません。
そこで今回は、BtoBサイトが目指すべきCVRの基準値やCVRが伸び悩む主な原因とそのチェックポイント、ユーザーの興味段階に応じた改善施策、優先順位の付け方と具体的な実行手順、施策実施時の注意点、さらには即実行できる10のチェックリストを網羅的に解説します。読み終えたときには、自社サイトの改善点とその打ち手が明確になり、成果につながる改善施策にすぐ着手できる状態になっているはずです。
Web経由の成果を最大化したいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
BtoBサイトのCVRとは
BtoBサイトのCVR(コンバージョン率)を正しく理解することは、成果につながる改善施策を考えるうえでの出発点となります。まずは、CVRの定義や算出方法、CVの具体例など、基礎的な内容を明確に把握しましょう。
定義
CVR・CV・CV地点は、それぞれ次のように定義されます。
| 項目 | 定義 |
|---|---|
| CVR | Webサイトに訪れたユーザーのうち、実際に目的のアクション(CV)を取った割合 |
| CV | ユーザーがサイト上で達成した成果地点(例:問い合わせや資料請求など) |
| CV地点 | ユーザーに達成してほしい具体的な行動や成果の着地点 |
BtoBサイトにおけるCVの具体例としては、資料請求、問い合わせ、ホワイトペーパーのダウンロード、セミナーやイベントへの申し込み、無料デモの申し込み、メルマガ登録、会員登録などが挙げられます。
どのアクションをCVとして定義するかはサイトや企業ごとに異なるため、自社のWebサイトでは何を成果地点とするのかを明確に定める必要があります。また、複数のCVを設定する場合には、それぞれの項目を明示し、関係者間で認識を統一することが重要です。
CVが不明確なままでは、どの施策が有効かを判断できず、CVRの向上や売上増加といった本来の目的に結びつけることが難しくなります。たとえば、CVが「問い合わせ完了」である場合と「セミナー申し込み完了」である場合では、打つべき施策の内容や優先順位が大きく異なります。
そのため、まずは自社サイトにおけるCVを正確に定義し、すべての施策の起点として認識することが、CVR改善に向けた最初の一歩です。
計算式
BtoBサイトのCVRは、次の計算式で求めます。
- CVR(%)=(CV数 ÷ セッション数)× 100
たとえば、1,000セッションのうち10件のCVが発生した場合、CVRは1%になります。
ここでいう「CV数」は、資料請求や問い合わせなど、成果地点としてあらかじめGoogle アナリティクス(GA4)などで「イベント」や「コンバージョン目標」として設定しておく必要があります。
また、CVを複数設定している場合には、それぞれのCVごとにCVRを個別で把握しておくと良いでしょう。たとえば、「問い合わせ完了」と「セミナー申し込み完了」をCVに設定している場合は、それぞれのCVRを分けて記録・分析することが、施策の精度を高めるために不可欠です。
個別のCVRを把握することで、どの成果地点にボトルネックが存在するのか、ユーザーがどのアクションに価値を感じているのか、具体的に把握できるようになります。こうした正確な数値管理こそが、CVRを改善していく上での土台となります。
BtoBサイトのCVRは「2%」を基準に考える
BtoBサイトにおけるCVRの目安として、まず意識すべき基準値は「2%」です。2023年にRuler Analyticsが公開した「Ruler Analytics|Conversion Rate by Industry」のデータによれば、BtoBサイトの業種別CVRは次のように示されています。
| カテゴリー | CVR | 内容 |
|---|---|---|
| B2B Ecommerce | 1.8% | 法人向けのオンライン販売サイト(業務用機器、資材、オフィス用品などの通販) |
| B2B Service | 2.7% | 法人向けに提供されるコンサル、金融、保険、教育、人材などの「無形サービス」全般 |
| B2B Tech | 2.3% | ソフトウェア、SaaS、ITインフラ、システム開発など法人向けの「技術製品・サービス」 |
このように業種によって差はあるものの、CVR2%という数値はBtoBサイトの初期目標値として設定するのに適しています。まずはこの数値を基準に、自社サイトのCVRがどの程度にあるかを把握し、改善の優先領域を見極めることが大切です。
たとえば、CVRが1%未満である場合には、まずはCVRそのものを引き上げる施策に注力する必要があります。フォームの改善、CTAの設計見直し、導線の最適化などが該当します。
一方で、すでにCVRが2〜3%以上に達している場合には、CVの母数を増やすこと、つまりサイトへの訪問者数を増やす施策(SEO・広告など)に軸足を移すことが望ましい判断となります。
CVRは無制限に上がっていくものではないため、自社のフェーズや目標に合わせて「改善すべきはCVRか、それとも集客か」を見極めながら、最適な施策にリソースを配分していくことが成果につながります。
CVRが上がらない主な原因とチェックポイント
BtoBサイトのCVRの基準である2%に到達していない場合、主な原因は次の3つに集約されます。
- ターゲット設定のズレ
- CTA(行動喚起)の設計ミス
- フォームや導線設計の煩雑さ
CVRを高めるには、単に一部のUIを修正するだけではなく、ユーザー行動全体を捉えた施策設計が欠かせません。なぜなら、CVの発生は複数の要素が連動して起こるため、一部の改善では十分な効果を得られないことが多いからです。
そのためには、Google アナリティクス(GA4)やMicrosoft Clarityといったツールを使い、データをもとに離脱箇所やボトルネックを可視化し、原因に即した改善施策を打つことが重要です。さらに効果的な改善を行うには、自社にとってのCV地点を正しく定義し、目的に応じて最適な導線設計やUIを選定する必要があります。
ターゲット設定のズレ
最初に確認すべきは、想定しているターゲットと実際に流入しているユーザーとの間にギャップがないかどうかです。狙いたい層と実際に訪れている層にズレがあると、コンテンツが響かず、CVRは上がりません。
CTA(行動喚起)の設計ミス
次に見直すべきは、ユーザーにとって「次に取るべき行動」が明確に示されているかどうかです。CTAが目立たなかったり、文言が曖昧だったりすると、ユーザーは迷い、CVに至りません。
フォームや導線設計の煩雑さ
最後に、CV直前の離脱要因として多いのがフォームや導線の複雑さです。入力項目が多すぎたり、目的地への遷移がわかりづらかったりすると、ユーザーの離脱率は高まり、CVには結びつきません。
最適な改善施策の可視化のためにはCV地点を明確にする
効果的なCVR改善を実現するためには、まず自社サイトにおける「CV地点」を明確に定義することが出発点となります。なぜなら、改善の方向性を誤る最大の原因は、CV地点を曖昧にしたまま施策を進めてしまうことにあるからです。
CV地点は企業によってさまざまで、複数の指標を設定しているケースもあります。BtoBサイトの場合、一般的に次のような行動がCV地点として設定されることが多いです。
- 資料請求
- お問い合わせ
- ホワイトペーパーのダウンロード
- メルマガ登録
- セミナー参加
- 無料デモ利用
- 会員登録
これらはどれもCVとして有効な指標ですが、ユーザーの興味段階や心理状態はCV地点ごとに大きく異なります。
たとえば、ホワイトペーパーをダウンロードするユーザーは情報収集段階にあり、導入検討までは至っていません。一方で、問い合わせを行うユーザーは、すでに導入を前向きに考えている段階であり、成約に近い存在です。
このように、CV地点ごとのユーザーの状態に応じて、改善すべき導線やUI設計、必要なコンテンツは大きく異なります。したがって、やみくもに改善施策を実行するのではなく、まずは自社におけるCV地点を洗い出し、整理してから施策を選定することが重要です。
興味段階別のBtoBサイト向けCVR改善施策
CVRを高めるには、ユーザーの興味段階に応じた施策の出し分けが不可欠です。なぜなら、ユーザーの心理状態やニーズの強さはCV地点によって大きく異なり、一律のアプローチでは効果が薄れるためです。各社で定義されるCV地点は異なりますが、大きく分けると次の4つの興味段階に分類できます。
- 興味・認知層(ホワイトペーパーのダウンロード、メルマガ登録)
- 比較・検討層(セミナーへの参加、無料デモ利用)
- 導入検討層(資料請求・問い合わせ)
- 継続利用層(会員登録)
CV地点が興味・認知層の場合
情報収集段階のユーザーには、まず気軽に接点を持ってもらうことが最優先です。まだ明確なニーズを持たない興味・関心層に対しては、「役立つ情報が得られる」「営業されない」という安心感を与える設計が重要です。
この層は将来的な見込み顧客となる可能性があるため、信頼関係の構築を軸に施策を考える必要があります。ここでは、ホワイトペーパーのダウンロードとメルマガ登録の2つの施策について解説します。
ホワイトペーパーのダウンロード
ユーザーにホワイトペーパーをダウンロードしてもらうには、「タイトル設計」と「完了ページでの導線設計」の2点が重要です。
ユーザーは、個人情報を提供する対価として価値ある情報を求めているため、ダウンロードしたいと思わせるだけの魅力を打ち出す必要があります。特にタイトルにはこだわり、「課題提起+メリット訴求」の構成で構成するのが効果的です。
たとえば、「失敗しないDX推進ガイド」ではなく、「DX推進に失敗する企業に共通する5つの落とし穴」のように、ネガティブ課題と解決策を組み合わせたタイトルが有効です。
また、完了ページも重要な接点です。「ダウンロードありがとうございました」だけで終わらせず、関連資料の案内やセミナー情報を提示し、さらなるアクションへ自然に誘導しましょう。
メルマガ登録
メルマガ登録は、フォーム項目を最小限にすることが基本です。情報収集段階のユーザーは慎重で、入力項目が多いと登録をためらう可能性があります。
入力項目は「メールアドレス」「名前」「会社名」程度にとどめ、心理的ハードルを下げるのが理想です。加えて、「営業は一切なし」「配信停止はワンクリックで可能」などの文言を記載し、安心して登録できるようにしましょう。
なお、目的によってはあえて項目を多く設定する方法もあります。入力の手間をいとわず登録してくれるユーザーは、ニーズが強いと判断できるため、精度の高いリード獲得につながります。
CV地点が比較・検討層の場合
比較・検討層のユーザーには、「信頼感」と「納得感」の提供が鍵になります。この層はすでに複数の選択肢を比較しており、自社に合うかどうかを見極めようとしています。
そのため、価格や実績、導入事例などの具体的な根拠を提示し、競合と差別化された強みを明確に伝えましょう。ここでは、「セミナーへの参加」と「無料デモ利用」のポイントを解説します。
セミナーへの参加
セミナー参加を促すには、「過去の参加者の声」「実績」「参加メリット」の提示が効果的です。時間を割いて参加する価値があると思ってもらうには、信頼に足る情報の提示が不可欠です。
また、申込フォームの項目は可能な限りシンプルにし、参加までのハードルを下げましょう。営業情報が必要な場合は、セミナー後のフォローアップで取得する流れを構築するのがおすすめです。
たとえば、セミナー資料のダウンロードで項目を増やしたり、次回セミナーや個別相談の案内を行ったりすることで、ユーザーの温度感を把握できます。
無料デモ利用
無料デモを促進するには、「フォーム項目の最小化」と「無料期間の余裕ある設定」が効果的です。まずは登録のハードルを下げ、必要な情報は後で取得する仕組みにしましょう。
また、導入企業のロゴや事例インタビューを掲載し、導入後の成果を具体的にイメージさせることも重要です。
無料期間は、14日〜1ヶ月程度に設定すると、申し込み率が向上します。逆に7日程度では試す余裕がなく、登録が後回しにされる可能性があります。
加えて、「使い方が分からず期間が終わる」ことを避けるため、オンボーディング施策の設計も忘れずに行いましょう。
CV地点が導入検討層の場合
導入検討層は、導入・契約の最終判断をしようとしている段階です。社内稟議や関係者の合意が必要になるため、「信頼性」と「対応の速さ」が求められます。
この段階のユーザーには、的確な情報提供とフォロー体制の構築が成果を左右します。ここでは「資料請求」と「問い合わせ」について解説します。
資料請求
資料請求を促すには、「入力項目の削減」「提供価値の提示」「信頼感の訴求」「即時対応体制の整備」の4点が重要です。
資料には、導入メリット・成功事例・機能比較など、社内稟議に必要な情報を網羅し、登録フォームではそれらが手に入ることを明示しましょう。さらに、資料請求があった際は即時対応できるように体制を整えておくことで、商談化率の向上にもつながります。
また、「社内稟議を通すための資料作成ノウハウ」などのコンテンツを同時に提供することで、ユーザーに伴走する姿勢が伝わり、信頼関係の構築にも貢献します。
問い合わせ
問い合わせは、最終的な意思決定に向けた重要なCVです。フォーム項目は必要最低限とし、「気軽に相談できる」印象を与えることが大切です。
導入検討層のユーザーは情報提供にも前向きですが、部署名や役職など過剰な入力を求めると離脱の原因になります。必要な情報は、やり取りの中で取得していく形で問題ありません。
また、問い合わせページには「導入実績」や「返信の早さ」など、信頼を裏付ける要素を明記しましょう。問い合わせ後の即時対応体制を整えることで、商談化・成約率の向上にも直結します。
CV地点が継続利用層の場合
継続利用層は、既に一定の関心を持っており、継続的な関係を築くことを目的としています。特にSaaSや継続型サービスにおいては、会員登録が起点になります。
この段階で最も重要なのは、「スムーズに登録してもらい、定着へつなげること」です。そのためには、フォーム項目の簡略化に加え、登録のメリットを明確に伝える必要があります。
例えば、会員限定イベントや非公開情報の提供など、登録による具体的な利点を提示することで継続率向上につながります。
さらに、登録ページや会員専用ページは直感的なUIにし、「使いやすそう」と思ってもらえる設計にすることが重要です。ファーストメールでは、再度メリットを伝えたり、人間味のあるメッセージを加えたりすることで、前向きな印象を与えることができます。
改善施策の優先順位と取り組み手順
CVRを効率よく改善するには、「成果に直結するポイント」から着手することが最も重要です。手をつけやすい箇所から施策を始めてしまうと、効果が出にくいだけでなく、成果に繋がらない修正に時間とリソースを費やしてしまいます。
施策の精度を高めるには、ツールによる定量的な分析を通じて、改善すべきポイントを客観的に把握したうえで進めることが成功への近道です。ここでは、CVR向上に向けて「優先順位の付け方」と「改善手順」を、5つのステップに分けて解説します。
- ステップ1:CV地点とコンバージョン経路を整理する
- ステップ2:CV地点に「近い箇所」から改善候補を洗い出す
- ステップ3:ツールを使って問題点を可視化する
- ステップ4:「CV地点への近さ × 改善難易度」で優先順位をつける
- ステップ5:改善→検証→再改善のサイクルを回す
ステップ1:CV地点とコンバージョン経路を整理する
最初に行うべきは、自社サイトの「CV地点」と「そこまでの導線」を正確に洗い出すことです。CVの定義と到達までの経路が曖昧なままでは、改善の優先順位を正しく判断できません。
BtoBサイトでは、資料請求や問い合わせ、ホワイトペーパーのダウンロード、セミナー申し込みなど、複数のCVが想定されます。そして、それらに至る経路は「コラム記事→導入事例→資料請求」や「ブログ→サービス紹介→問い合わせ」など多岐にわたります。
自社サイトの中で、実際にユーザーがどのような流れでCV地点に到達しているのか、また、想定した導線通りに遷移しているのかを確認することが、改善施策の精度とスピードを大きく左右します。
ステップ2:CV地点に「近い箇所」から改善候補を洗い出す
次に、CVの直前でユーザーが離脱している箇所に注目し、改善の優先候補を洗い出します。
ここで大切なのは、「対応しやすい場所」からではなく、「CV直前のボトルネック」から着手することです。たとえば、次のような要素は、典型的な改善対象になります。
- 問い合わせページへの導線が目立たない
- フォームの必須項目が多すぎる
- 資料請求ボタンを押したあとの読込時間が長い
- CTA文言が不明瞭でアクションを促せていない
このように、CVに最も近い場所でユーザーの離脱が起きていないかを可視化し、改善箇所を洗い出すことで、CVRの向上に直結する改善が可能になります。
ステップ3:ツールを使って問題点を可視化する
改善候補が洗い出せたら、次はツールを用いて「客観的なデータ」に基づき問題点を特定しましょう。感覚や憶測に頼ると、効果的な優先順位付けが難しくなります。
Google アナリティクス(GA4)では、「CVRが低いページ」や「直帰率が高いページ」を特定できます。また、Microsoft Clarityを使えば「どこがクリックされているか」「どこまで読まれているか」など、ページ内でのユーザー行動が可視化されます。
これらのツールを組み合わせることで、離脱が多いページやセクションを特定でき、改善すべき具体的なポイントを客観的に把握できます。感覚ではなく、データに基づく判断が、成果につながる改善を可能にします。
ステップ4:「CV地点への近さ × 改善難易度」で優先順位をつける
改善箇所が明らかになったら、それぞれの施策に対して「CV地点との近さ」と「改善の難易度」を掛け合わせて優先順位を決定します。
たとえば、「問い合わせボタンを目立たせる施策」があっても、開発リソースや外注が必要で難易度が高い場合、他の低コストかつ即実行できる施策を優先すべきです。優先順位の整理は、次のように考えると効率的です。
- 近くて簡単 → すぐに実施(例:CTA文言の変更)
- 近くて難しい → 計画を立てて実施(例:ボタン配置変更)
- 遠い → 状況を見て判断(例:ブログデザイン調整)
ただし、CV地点から遠くても離脱率が著しく高いページや、CV経路に関与している可能性があるページは例外です。近い箇所の改善後に着手する形で、優先順位を柔軟に調整しましょう。
ステップ5:改善→検証→再改善のサイクルを回す
優先順位に沿って改善施策を実行した後は、必ず検証を行い、次の改善に活かす「改善サイクル」を回しましょう。
CVRの向上は、一度の施策で完結するものではありません。施策ごとに結果を分析し、「上手くいったかどうか」「さらに改善すべきか」を確認し続けることが、持続的な成果を生む鍵となります。
検証には、Google アナリティクス(GA4)やMicrosoft Clarityに加え、A/Bテストができる「LOGLY Audience Analytics」や「Optimize Next」といったツールも活用しましょう。これらのツールを活用すれば、施策の前後での数値変化や、ユーザー行動の変化を可視化することができます。
改善効果が薄かった場合は、ステップ2に立ち戻り、CVに近い別の課題を洗い出して改善施策を再実行します。この「改善→検証→再改善」のループを回すことこそが、BtoBサイトのCVR向上に必要な本質的な取り組みです。
施策実施前後で活用したいおすすめツール
CVR改善を成功させるためには、施策前後における正確な現状分析と効果検証が不可欠です。そのためには、ツールを活用して定量的にユーザー行動を把握し、改善ポイントや成果を可視化することが重要です。
本章では、施策実施「前」、施策の「検証時」、そして「施策後」の3つのフェーズに分けて、CVR向上に役立つおすすめツールを紹介します。
施策実施「前」におすすめのツール
まずは、改善施策に着手する前に活用したい、次の2つの解析ツールを紹介します。
- Google アナリティクス(GA4)
- Microsoft Clarity
Google アナリティクス(GA4)
Google アナリティクス(GA4)は、無料で利用できる代表的なアクセス解析ツールです。CVRの低いページや直帰率の高いページを特定することで、どこに改善余地があるかを明らかにできます。
流入経路別のCVRや、検索エンジン・広告・SNSなどのチャネル別効果も可視化できるため、流入元とCVの関係を把握するのに最適です。また、個別のページにおけるユーザー行動を可視化し、改善対象を絞り込むことができます。
公式サイト:https://developers.google.com/analytics?hl=ja
Microsoft Clarity
Microsoft Clarityは、ユーザーのページ内行動を可視化できるヒートマップツールです。特に、「どこでスクロールが止まり、どの部分がクリックされているか」を直感的に分析できる点が特徴です。
クリックの集中や離脱ポイントを把握することで、UI改善やコンテンツ配置の見直しに役立ちます。GA4ではわからない「ユーザー行動の質」まで分析できるため、組み合わせての活用がおすすめです。
公式サイト:https://clarity.microsoft.com/lang/ja-jp
施策の「検証(A/Bテスト)時」におすすめのツール
次に、施策実行後の効果検証として活用できるA/Bテストツールを紹介します。
- LOGLY Audience Analytics
- Optimize Next
LOGLY Audience Analytics
LOGLY Audience Analyticsは、無料で使えるA/Bテスト対応ツールで、ユーザー属性や行動データをもとにWebサイトの最適化を支援してくれます。設定が簡単で、直感的にテストが実施できるため、スピーディな検証が可能です。
さらに「BtoB分析」機能を活用すれば、企業単位で訪問状況を分析でき、業種別に導入事例を出し分けるといった細かな改善も実現できます。
公式サイト:https://juicer.cc/
Optimize Next
Optimize Nextは、Google Optimizeの後継ツールとして登場した、無料のA/Bテストおよびパーソナライズツールです。Google アナリティクス(GA4)と連携することで、テスト結果を手軽に把握でき、分析効率も高まります。
また、専用のブラウザ拡張機能を使えば、HTML・CSSの調整や要素の配置変更などをノーコードで実行可能です。
公式サイト:https://optimize-next.com/
施策実施「後」におすすめのツール
最後に、施策を実施した後のリード育成や商談管理に役立つMA・CRMツールを紹介します。
- Hubspot
- Sales force
Hubspot
Hubspotは、無料プランでも導入できる高機能なマーケティングオートメーション(MA)ツールです。CV後のユーザーに対し、メール配信や営業連携といったナーチャリング施策を自動で実行できます。
また、CVRだけでなく「その後の商談化率」や「営業フローの効率性」まで検証できるため、マーケティングROIの最適化にもつながります。
公式サイト:https://www.hubspot.jp/
Sales force
Salesforceは、世界中で活用されている業界最大手のCRM(顧客管理システム)です。CV後のリードを一元管理でき、商談進捗や成約状況もリアルタイムで可視化可能です。
施策によって獲得したリードが、どのような経路で商談・成約に至ったのかを追跡できるため、施策ごとの費用対効果を明確に測定できます。30日間の無料トライアルもあり、導入ハードルが低いことも魅力です。
公式サイト:https://www.salesforce.com/jp/
アクトデザインラボが伴走支援した会社の事例
アクトデザインラボでは、BtoB分野で事業展開する企業に対し、CVR改善に特化した伴走支援を数多く提供してきました。見た目の刷新や単なる集客施策にとどまるのではなく、「CVRを確実に向上させるために何をどう改善すべきか」という本質的な課題に踏み込み、具体的な成果を生み出すことに注力しています。
ここでは、支援の結果として高い成果を挙げた2社の事例を紹介します。
総合電材商社の成功事例:電話対応の強みを活かしてCVRを約2倍に改善
総合電材商社では、「問い合わせの獲得」をCV地点としてリスティング広告とSEOによる集客を行っていましたが、CVRが思うように上がらず、投資対効果に課題を抱えていました。
そこで、アクトデザインラボでは、同社の強みと顧客ニーズを把握するために、社内の担当者や関連部署にヒアリングを実施しました。その結果、全国対応が可能であることや、電話応対に強みがあることが明らかになりました。この強みに着目し、フリーダイヤルを新たに取得してWebサイトに掲載し、電話での問い合わせが可能な導線を整えました。
その結果、施策実施前と比べてCVR(有効問い合わせ数÷セッション数)は約2倍にまで改善されました。成果を上げた要因は、新たに施策を追加したことではなく、自社の強みを踏まえてCV地点そのものを「電話での問い合わせ」に最適化した点にあります。
物流会社の成功事例:情報収集層へのアプローチでCVRを約2.5倍に改善
次に紹介する物流会社では、コーポレートサイトからの流入が安定しており、一定の問い合わせ件数は獲得できていました。しかし、さらなる成長のために、見込み顧客とのより多様な接点を作りたいという課題を抱えていました。
アクトデザインラボは、ライト層(情報収集層や比較検討層)との接点強化に着目し、従来の「問い合わせ」中心のCV地点だけでは不十分であると判断しました。これまでの導線では導入検討層とは接触できても、情報収集段階のユーザーとは関係を築けていなかったためです。そこで、ホワイトペーパーのダウンロード施策とセミナーの開催を新たに導入しました。
結果として、CVR(有効問い合わせ数÷セッション数)は、施策実施前の約2.5倍にまで改善されました。この成果は、いきなり問い合わせを求めるのではなく、ユーザーの興味段階に合わせて段階的に関係を構築するアプローチが功を奏した結果です。
ターゲットユーザーの「実態」と自社の「強み」を正確に捉えたことが成功の鍵
紹介した2つの事例に共通していることは、ターゲットユーザーの実態と自社の強みを正確に把握し、それに基づいて施策を選定・実行したことです。
総合電材商社では、「電話対応のスムーズさ」という強みを見出し、即時性のあるコミュニケーション手段としてフリーダイヤルを設置することで、ユーザーの心理的ハードルを下げることに成功しました。
物流会社では、情報収集層や比較検討層が求めている情報を適切に提供することで、ホワイトペーパーやセミナーという間口を通じて自然な接点を構築し、成果へとつなげました。
ターゲットユーザーの状況を的確に読み解き、自社の価値をどう届けるかを戦略的に設計したことが、CVR改善の大きな成果につながりました。
BtoBサイトのCVR改善施策を実施する際の注意点
ここまで、BtoBサイトのCVRを向上させるための施策や、取り組み手順・優先順位の付け方について解説してきました。
ここでは、施策を実行する前に必ず押さえておきたい注意点について解説します。以下の3点を理解した上で改善を進めることで、無駄な工数を省き、成果につながる確実な取り組みが可能になります。
- LP制作の前に戦略と設計を明確にする
- ユーザーの使いやすさを最優先にしたデザインを採用する
- 成果に直結する部分から優先的に改善を行う
これらのポイントを見落としたまま施策を進めてしまうと、期待する成果が得られなかったり、不要なコストや時間が発生したりする可能性があります。ここでは、それぞれの注意点を詳しく解説します。
LP制作の前に戦略と設計を明確にする
CVR改善策としてLP(ランディングページ)を制作する場合、まずは戦略と設計の整理を行った上で制作に着手することが重要です。
LPの制作自体は効果的な施策の一つですが、「何をCVとするか」「どのターゲットに向けたLPか」といった基本設計を固めずに進めると、訴求軸や導線設計がぶれてしまい、結果としてCVにつながらないページが出来上がってしまいます。
さらに、流入元やユーザーの行動パターンも含めて設計を行うことで、ユーザーにとって自然な流れでCV地点へ誘導することが可能になります。たとえば、どのページから流入し、どこまでスクロールされ、どの要素がクリックされているかを把握することが、最適な構成やCTA設計に直結します。
戦略と設計に基づいて構成・導線・CTAを丁寧に設計することが、成果につながるLPをつくるための出発点となります。
ユーザーの使いやすさを最優先にしたデザインを採用する
Webサイトを改善する際は、自社メンバーの好みを優先したデザインにするのではなく、実際にサイトを利用するユーザーの視点を最優先にする必要があります。
確かに社内メンバーの意見も重要ですが、最終的に成果に直結するのはユーザーの使いやすさです。たとえば、次のような観点から、客観的にデザインの妥当性を検討しましょう。
- スマートフォンでも問題なく閲覧できるか
- フォントや文字サイズが読みやすいか
- フォームの入力がスムーズにできるか
- ナビゲーションが直感的に理解できるか
- サイト内を3クリック以内で移動できるか
「世界観を伝える」「おしゃれに見せる」といった目的だけでデザインを考えてしまうと、かえってユーザーの利便性を損なう恐れがあります。常に「この構成はユーザーにとって明快か」「操作しやすい設計になっているか」と問い直しながら進めましょう。
また、Microsoft Clarityなどのユーザー行動分析ツールを使えば、感覚に頼ることなく、定量的なデータをもとに判断できます。ユーザー視点に立った設計と、データに基づく客観的な検証を組み合わせることが、CVR向上への鍵となります。
成果に直結する部分から優先的に改善を行う
改善施策を検討する際は、取り組みやすさではなく、CVに最も近いボトルネックから着手することが最も重要です。「トップページの画像を差し替える」や「全体の色味を調整する」といった施策は着手しやすく感じますが、直接的な成果にはつながりにくい場合が多く、優先度は低いと判断すべきです。
CVに近い箇所の改善とは、ユーザーがアクションを起こす直前にある要素の見直しを指します。具体的には、次のような施策が挙げられます。
- 問い合わせフォームの項目数を減らす
- CTAボタンの配置や文言を調整する
- セミナー申し込み導線の視認性を高める
このような改善は、ユーザーの行動に直接作用するため、高い成果につながりやすくなります。
また、優先順位を判断する際には、Google アナリティクス(GA4)やMicrosoft Clarityなどのツールを使って、CV地点に近い箇所のユーザー行動データを分析することが必要です。
CVに直結しない要素を闇雲に改善するのではなく、「CV地点への近さ」と「改善の難易度」という2軸で優先順位を整理し、効果的な施策から実行していくことが、着実な成果を得るための最適なプロセスです。
BtoBサイトのCVRを最適化するための10のチェックリスト
最後に、記事を読み終えた直後からすぐに取り組めるよう、CVR最適化のための10のチェックリストをまとめました。1つ1つ確認しながら、自社サイトの状態と照らし合わせてみてください。
| No. | チェックリスト | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 自社にとってのCV地点を定義し、現在のCVRを数値で把握している | 成果を正しく評価するために、CV地点と現状のCVRを把握しているかを確認します。 |
| 2 | CV地点が複数ある場合、それぞれに対してKPI(件数・CVR)を設定している | CV地点ごとにKPIを設定し、改善の進捗と成果を評価できる状態かをチェックします。 |
| 3 | ペルソナを具体的に設計し、施策に反映している | ターゲットの属性や課題を明確にし、コンテンツや導線設計に落とし込めているかを確認します。 |
| 4 | CTAボタンが視認性・文言の両面で最適化されており、ユーザーの行動を促せている | ボタンの配置や色・文言が適切で、次のアクションへスムーズに導けているかを確認します。 |
| 5 | 離脱ポイントを特定し、適切な改善策を施している | 離脱が多いページやセクションに対して、明確な改善アクションを取れているかを確認します。 |
| 6 | PC・スマホ・タブレットいずれのデバイスでも快適に閲覧・CVできる設計になっている | モバイル環境を含むあらゆるデバイスで、スムーズにコンテンツ閲覧・CVできるかを確認します。 |
| 7 | 興味段階に応じた情報(導入事例・比較表・FAQなど)を適切に用意している | 検討段階ごとのニーズに対応した情報設計がなされているかをチェックします。 |
| 8 | 導入実績や顧客の声など、信頼を醸成するコンテンツを十分に掲載している | ユーザーの不安を払拭し、導入への後押しとなる信頼情報が整っているかを確認します。 |
| 9 | コンテンツの終点に「問い合わせ」や「資料ダウンロード」などのCV導線を明確に設置している | 記事やページ単位でゴールが設計されており、ユーザーが次のアクションを取りやすくなっているかを確認します。 |
| 10 | Google アナリティクス(GA4)やMicrosoft Clarityなどを活用し、データに基づいて判断を行っている | 感覚ではなく定量データに基づいてCVR改善の判断ができているかをチェックします。 |
まとめ
戦略設計から施策実行、検証方法に至るまでを、体系立てて解説しました。併せて紹介した10のチェックリストも活用することで、具体的な着手ポイントが明確になり、実行フェーズへとスムーズに移行できます。
BtoBサイトのCVRを継続的に向上させるには、感覚的な施策や一時的な対応では成果につながりません。成果を出すためには、自社の目的と状況に応じた戦略的な改善プロセスを構築し、順序立てて取り組むことが欠かせません。
まず重要なのは、自社にとってのCV地点を明確に定義し、何をもって成果とするかを全関係者で共通認識として持つことです。次に、施策の実行にあたっては、やりやすさではなく成果に直結する箇所から優先的に改善を行うことが求められます。そして、改善施策の効果を適切に検証し、その結果に基づいて継続的に改善を回していける体制を整えることが、CVR向上の土台になります。
自社サイトのCVRを本気で改善したいと考える方にとって、今回ご紹介した内容は確かな指針となるはずです。社内だけで取り組むことに不安がある場合や、専門的な視点を取り入れながら進めたいとお考えの場合は、BtoBサイトの改善支援に豊富な実績を持つ「アクトデザインラボ」まで、お気軽にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な改善ステップをご提案いたします。