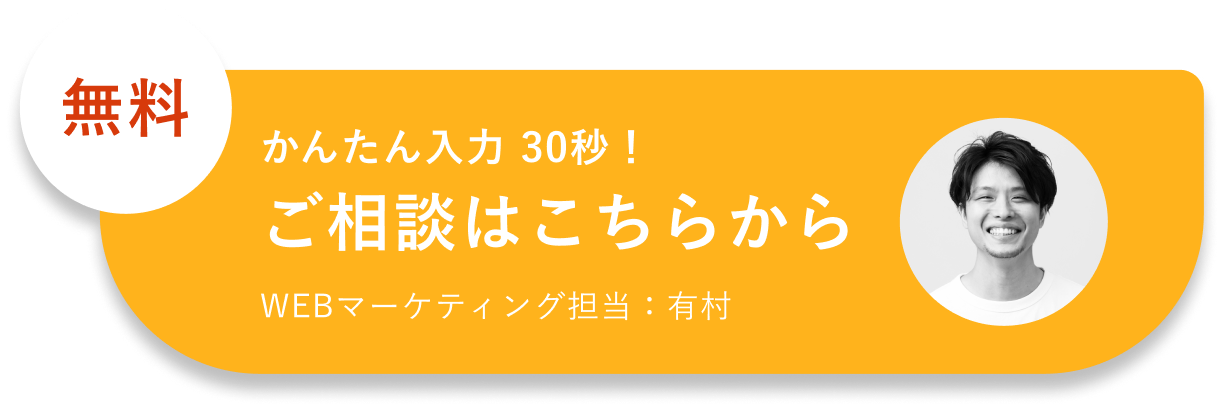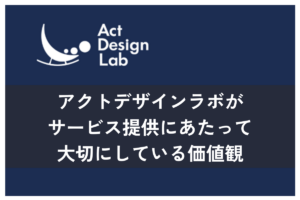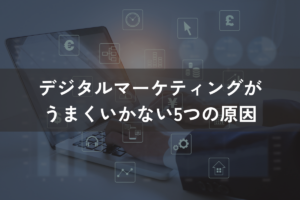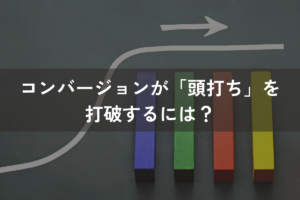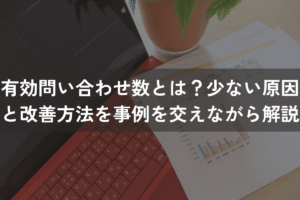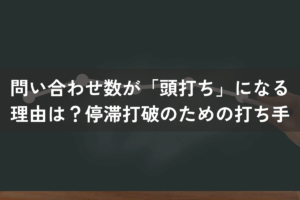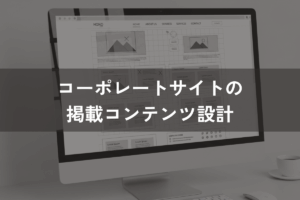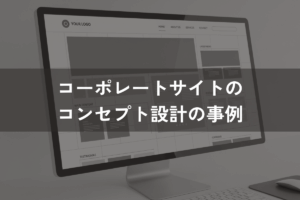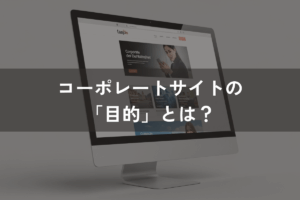「せっかくLPを作ったのになかなか成果が出ない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?新規で立ち上げたLPが最初から上手く機能することは少なく、タイミングをみてLPO(ランディングページ最適化)に取り組むことが重要です。
今回は、LPOの基本情報からLPOを実施すべきタイミングやLPOの進め方・具体策まで詳しく解説します。「LPOってそもそも何のこと?」「LPOに取り組みたいけど進め方がわからない」と思っている人は必読です。LPOの実施事例も紹介するので、具体的なイメージを掴んで実務に活かしてみましょう。
LPOとは
LPOとは「Landing Page Optimization」の略称で、ランディングページ最適化と訳されます。 LPの内容をユーザーニーズに合わせて改善することを指し、主にCVR(コンバージョン率)向上を目的に行われます。
コンバージョンにつなげるためには、いかにユーザーにページに滞在してもらい、コンテンツを読んでもらい、商品に興味をもってもらうかが重要です。そのためには、ユーザーニーズに沿ったページの構成やデザインにしていく必要があり、これこそがLPOなのです。
ここでは、LPOと混同されがちなSEO・EFOとの違いと、LPOの重要性について解説します。
SEOとの違い
SEO(Search Engine Optimization)は「検索エンジン最適化」のことで、LPOとは目的とアプローチ方法が異なります。
SEOの目的は、サイトへの集客、つまり訪問者数を増やすことです。そのために、検索結果での上位表示を目指して検索エンジンに評価されやすいサイト改善を行います。一方、LPOはCVR向上を目的にユーザーニーズに沿ったLP改善を行うことを指します。
SEOによって集客力を高め、LPOで効率よくコンバージョンにつなげるというように、SEOとLPOの両方に取り組むことで効果を最大化できます。
EFOとの違い
EFO(Entry Form Optimization)は、「エントリーフォーム最適化」のことで、CVR向上を目的としている点はLPOと同じですが、EFOでは入力フォームの改善を行います。
入力フォームとは、購入や申し込みの際に、住所やクレジットカード情報などを入力するためのフォームのことで、この入力フォームが使いづらいとユーザーの離脱につながってしまいます。EFOでは、フォームの項目数を減らしたり、入力例を記載したりすることでユーザーのストレスを減らし離脱防止を図ります。
入力フォームはコンバージョンの一歩手前の段階で、ここでユーザーを逃してしまうのは非常に惜しいため、入力フォームを設置しているサイトでは、LPOと併せtEFOにも取り組むことが多いです。
LPOが重要な理由
集客施策でいくら訪問者数を増やしても、ページに飛んできてすぐに離脱されていては意味がありません。ユーザーに、「このページには欲しい情報がありそうだ」と思ってもらい、読み進めてもらうためにはLPOが必要なのです。
また、LPOを実施して効率よくコンバージョンにつなげることができれば、費用対効果は上がります。集客施策を無駄にせず、効率よくマーケティングを実施するためには、LPOは欠かせない施策といえるでしょう。
LPOを実施すべきタイミング
LPを立ち上げたもののCVRが上がってこないと、「急いでLPOを実施しないと!」と焦ってしまうかもしれませんが、もしかするとまだLPOを実施するタイミングではないかもしれません。
LPOは適切なタイミングで実施することで効果を最大化できるため、ここで紹介するタイミングと自社の状況を照らし合わせてみてください。
- 集客施策を最適化できたとき
- CVRが低いとき
- LPの離脱率が高いとき
- 新しいプロモーションを始めるとき
1. 集客施策を最適化できたとき
LPOは、サイトへの集客施策が最適化され、ある程度のセッション数が確保できた段階で実施すると効果的です。なぜなら、下表の①ように、セッション数が少ない段階でLPOを実施してCVRを高めても、大きな効果は期待できないからです。
| セッション数 | CVR | コンバージョン数 | |
|---|---|---|---|
| ① | 1,000 | 1%⇒2% | 10⇒20 |
| ② | 10,000 | 1%⇒2% | 100⇒200 |
焦って①の段階でLPOを実施しても、セッション数を伸ばさなければコンバージョン数は増えてこないので、結局また集客施策に力を入れなければならなくなります。
また、広告での集客は、どこかで頭打ちになるタイミングがきます。セッション数を増やすためにターゲットを広げすぎると、コンバージョンにつながりにくいユーザーが増えてしまうからです。
SEOや広告などの集客施策が最適化されたタイミングでLPOを実施すると、コンバージョン率を上げることで効率よくコンバージョン数を稼げる仕組みができ上がります。
2. CVRが低いとき
当然ともいえますが、CVRが低いときや、下がってきたときがLPOを実施すべきタイミングです。CVRの平均値は2~3%といわれていますが、業界によって差があるため、業界平均と比較してみると良いでしょう。
ターゲットに近いユーザーを集客できているはずなのに、CVRが伸びてこないというときは、LPのコンテンツやデザインがユーザーニーズにマッチしていない、もしくはコンバージョンに至るには十分でないことが考えられます。LPOを実施し、ユーザーの期待に応えるLPに改善することで、大きな成果が見込めます。
3. LPの離脱率が高いとき
セッション数は確保できているものの、離脱率が高い場合もLPOを実施すべきタイミングといえます。離脱率が高い場合、広告経由で流入したものの求めていた情報がなかった、というように、LPの訴求ポイントがユーザーニーズとずれてしまっていることが考えられます。
この場合、LPOで離脱ポイントを明確にし、改善策を実施することで、離脱率を下げることができます。離脱率が下がると、ページ滞在時間が伸び、コンバージョンにつながりやすくなるため、CVR向上が期待できます。
4.新しいプロモーションを始めるとき
新しいプロモーションを始めるときは、クリエイティブも変わることが多いため、LPOを同時に実施することがおすすめです。広告のクリエイティブにLPを合わせるだけでなく、ターゲットニーズを捉えてコンテンツの順番を入れ替えることも有効です。
たとえば、新客向けのプロモーションを始める場合は、ブランドへの信頼感を醸成できるような権威づけのある訴求やブランド紹介コンテンツの表示位置を上げるというような工夫をしてみましょう。
また、新しいプロモーションを始めると、広告投入などで大幅な流入が見込めるので、LPOを実施しておくことで、プロモーションの成果を最大化できます。
LPOのやり方6ステップ
LPOで成果を出すためには、仮説と検証を繰り返すことが非常に重要です。一つの施策を実施したからといってすぐに効果が出ることは少なく、細かい改善を繰り返しながら徐々に最適化が図られます。
とはいえ、時間をかけて成果が出るまでゆっくり取り組むという余裕はない場合が多いのではないでしょうか?ここでは、できるだけ効率的に、スピーディーに成果につなげるためのLPOの進め方を紹介します。一見面倒に思えるかもしれませんが、この6ステップを踏むことでPDCAを回しやすくなり、成果につながるLPOが実施できます。
- ステップ1:ターゲットを明確にする
- ステップ2:KPIを明確にする
- ステップ3:現状分析を行い課題を抽出する
- ステップ4:仮説を立てて改善策を検討する
- ステップ5:改善策に優先順位をつけて実行する
- ステップ6:検証を行いPDCAを回す
ステップ1:ターゲットを明確にする
CVRを上げるためには、確度の高いユーザー、つまりコンバージョンにつながる可能性が高いユーザーに焦点を当てることが大切です。そのためには、ターゲットを明確にして、関係者全員の共通認識とすることが必須です。
ターゲットを明確にしたうえで、ユーザーの悩み・知りたいことは何か、どんな情報があれば解決できるか・満足できるか、どのように情報を提供すれば納得性が高まるかを考えていきましょう。
ターゲットが明確になっていないと、現状分析や仮説検証をする際もユーザー視点が欠けてしまい、LPOの効果が薄れてしまいます。LPOを実施する前に、まずはターゲットを明確にしましょう。
ステップ2:KPIを明確にする
KPIを明確にしておくことも重要です。KPIが曖昧なままLPOを実施してしまうと、効果検証の際、十分な成果が得られたのかどうか判断がつかなくなってしまいます。
KPIは事業目標から逆算して設定することが大切です。たとえば、事業目標として「ECサイトでの売上120%伸長」と置いている場合、事業目標を達成するためには、LPOを実施することでどこまでコンバージョン数を獲得すればよいか、CVRを上げればよいかを考えましょう。
KPIは、「6月までにCVRを0.5%伸長させる」というように、いつまでに、どの指標で、どの値を目指すのかを明確にすることが大切です。これにより、実施する改善策が決めやすくなり、効果検証もスムーズに進められます。
ステップ3:現状分析を行い課題を抽出する
ターゲットとKPIが明確になったら、解析ツールを活用してLPの現状を分析しましょう。見るべき主な指標は次のとおりです。
- 閲覧数
- 滞在時間
- 直帰率
- 離脱率
- ユーザー行動(離脱箇所・スクロール状況など)
- 流入経路
- 流入キーワード
- CVR
- ユーザー属性
- 使用デバイス
流入キーワード別のCVRや、ユーザー属性別のCVR等、ターゲットを意識しながら分析してみましょう。また、分析をする際は、過去の数値や競合の数値、業界平均など比較対象を置くことが重要です。「なんとなくこの数値だと低そう」などと、感覚的に判断しないように注意しましょう。
ステップ4:仮説を立てて改善策を検討する
ステップ3で明らかになった課題に対して、仮説を立てていきます。たとえば、滞在時間が以前に比べて落ちてきている場合、次のような仮説が立てられます。仮説を立てる際は、ユーザー目線に立ってページを読んでみたり、競合サイトと比較してみたりすることも有効です。
- ファーストビューの魅力が足りないのではないか
- ユーザーニーズに対応したコンテンツになっていないのではないか
- ページ内にCTAが多く読みづらいのではないか
- ページの表示速度が遅いのではないか
まずは考えられる仮説を列挙して、それぞれに対応する改善策を検討しましょう。
ステップ5:改善策に優先順位をつけて実行する
検討した改善策は、優先順位をつけて、KPI達成のために効果が高そうなものから着手していきます。
改善策は、できれば一つずつ実施することをおすすめします。同時に複数実施してしまうと、効果が出てもどの施策の効果なのかわからなくなってしまうためです。優先順位に悩んだ時は深く考えすぎず、先に準備ができそうなものや実装が簡単なものからどんどん実施していきましょう。
ステップ6:検証を行いPDCAを回す
改善策を実行して、ある程度データが蓄積したタイミングで効果検証をします。効果が出た場合は継続し、効果が出ていない場合は、原因を探索し、軌道修正をしましょう。そして、また効果検証をします。
LPOは、一度実施して終わりではなく、効果検証と修正を繰り返しながら継続して実施することで徐々に最適化が図られます。
LPOの具体施策
LPOで効果が期待できる具体策を紹介します。
前章で解説したように、改善策は、分析結果と仮説に基づいて検討することが大切です。「なんとなくファーストビューに課題がありそうだから改善してみよう」というような曖昧な理由で進めることは避けましょう。PDCAがうまく回らなくなってしまいます。
- ファーストビューを魅力的にする
- CTAを最適化する
- 検索ニーズに応えるコンテンツを増やす
- コンテンツの順番を入れ替える
- 入力フォームを最適化する
- ページの表示速度を上げる
1. ファーストビューを魅力的にする
ユーザーはファーストビューでそのページを読むかどうかを決めます。「知りたい情報がありそうだ」という印象を直感的に与えられるのが、良いファーストビューの条件です。
画像は、商品のベネフィットや世界観がひと目でわかるようなものを選びましょう。キャッチコピーは、「ユーザーのどんなニーズに応えるのか」「どんなベネフィットがあるのか」を端的に表現したものが良く、具体的な数値や権威性のあるワードを入れ込むと効果的です。
ファーストビューの情報量は、多すぎても少なすぎても良くありません。瞬時に読み取れる情報量かつ、情報が完結しているということを意識しましょう。また、広告との整合性を取ることも大切です。広告から遷移してきたユーザーが違和感のないように表現やデザインに統一性を持たせましょう。
2. CTAを最適化する
CTAとはCall To Actionの略で、ユーザーがコンバージョンに至るために押すボタンのことを指します。CTAを工夫することで、CVRが大きく伸びることもあります。ボタンの文言・デザイン・位置・数を工夫しましょう。
ボタンの文言は、「購入する」「お申込みはこちら」など端的でわかりやすい文言にします。CTAの上に、「先着○○名様限定」「今なら○○プレゼント」などのクリックを促すような一文を入れることも効果的です。
ボタンの色や形は、LPデザインやユーザー層にマッチするように工夫しましょう。ボタンの角が丸角か四角かによってもユーザーに与える印象は異なります。
ボタンの位置や数は、ユーザーの視線やスクロールの動きを想定しながら検討しましょう。ユーザーが購入やお問い合わせなどの行動を取ると想定される箇所に複数設置すると良いですが、多すぎるとページが見づらくなるので注意が必要です。
3. 検索ニーズに応えるコンテンツを増やす
多くの場合、ユーザーは、LP内のコンテンツを読みながら購入するかしないか、問い合わせをするかしないかを検討します。そのため、ユーザーの判断材料になるようなニーズにマッチしたコンテンツを提供することが非常に重要です。
たとえば、衣類を扱っているECサイトの場合、ユーザーは「着こなせるだろうか」「サイズで失敗したくない」と考えながらページを見ているでしょう。その場合、ユーザーの不安を解消しニーズを満たすには、モデルの着用画像だけでなく、一般人に近いようなスタッフの着用画像や口コミを多数掲載する方が良いと考えられます。
ユーザーのニーズを意識した良質なコンテンツを十分な数準備することが大切です。
4. コンテンツの順番を入れ替える
ファーストビュー以下では、優先順位をつけてユーザーがコンバージョンに至るまでに必要なコンテンツを並べていきます。コンテンツが揃っていても、表示順がユーザーのニーズとマッチしていないことがよくあります。
たとえば、ダイエット食品のECサイトでは、ユーザーは「本当に効果あるの?」と思いながらページを読み進めていくと想定されます。にもかかわらず、体験談がページ下部に配置されていたら、体験談にたどり着くまでに離脱してしまうでしょう。
ユーザーの頭の中を想像しながら、コンテンツの表示順を精査しましょう。
5. 入力フォームを最適化する
入力フォームを設置している場合は、EFOを実施することも効果的です。次のポイントを参考にしてみてください。
- 項目数は最低限にする
- 必須項目に「必須」と表示する
- 入力例を入れる
- 住所は郵便番号から自動入力できるようにする
- エラー表示は訂正箇所がひと目で分かるようにする
- 離脱につながる不要なリンクやバナーは入れない
- スクロールが少なくてすむよう縦幅をできるだけ短くする
6. ページの表示速度を上げる
ページの表示が遅く、読み込む前にページを閉じてしまったという経験は誰でもあると思います。ページの表示速度が遅いとユーザーはストレスを感じ、すぐに離脱してしまいます。
ページの表示速度はGoogleが提供する無料ツールPageSpeed Insightsで簡単に計測できます。計測したいページのURLを入力すると、モバイル・パソコンそれぞれの表示速度を計測することができます。表示までに3秒以上かかっている場合は、改善に取り組みましょう。競合サイトの表示速度も確認できるので、参考にしてみてください。
表示速度を短縮するには、画像や動画のサイズの最適化、HTMLやCSS、JavaScriptなどの見直しが必要です。取り組めるものから改善してみましょう。
7. モバイル対応を強化する
LPにアクセスしているデバイスの状況を確認してみましょう。一般消費者向けのLPでは、圧倒的にモバイルからのアクセスが多いはずです。
LPを制作する際は、モバイル画面での使いやすさ、見やすさを確認する必要があります。文字や画像のサイズをスマートフォン用にするだけでなく、スクロール追従型のCTAボタンを設置する等、スマートフォンユーザーの行動を考えながら改善していきましょう。
LPOを成功させるためのポイント
「LPOを実施してもなかなか効果が出ない」と悩んでいる人は、次のポイントを確認してみてください。
- 商品・サービスの訴求ポイントを明確にする
- ユーザー視点を常に意識する
商品・サービスの訴求ポイントを明確にする
訴求ポイントは、できる限り無駄な要素をそぎ落とし、直感的に価値を感じてもらえるようなシャープな表現にしましょう。
商品・サービスの担当者にとっては、わかりやすく魅力に感じる訴求ポイントでも、初めて見る人にとっては難しくてよくわからないということはよくあります。商品・サービスの特徴や価値をかみ砕いて、何度もブラッシュアップを重ねましょう。
LPのファーストビューで伝えられる情報は限られています。本当に伝えたいポイントに絞って、魅力的なワードで訴求して初めてユーザーに価値が伝わり、コンバージョンにつながります。
ユーザー視点を常に意識する
LPOに取り組む際は、ユーザー視点を常に意識してください。ユーザー視点が欠けた企業本位のLPは、ユーザーがストレスを感じて離脱しやすくなるだけでなく、企業やブランドに対するイメージダウンにもつながりかねません。
次のポイントを意識しながら、ユーザーになりきってLPを見てみましょう。
- ユーザーが迷わない導線を引けているか
- ユーザーにとってわかりづらい表現はないか
- ユーザーニーズにマッチしていない不要なコンテンツはないか
- モバイル表示で見づらい箇所はないか
アクトデザインラボが実施したLPO実施事例
当社アクトデザインラボは、LPOの計画立案から実施、解析まで一括して請け負い、クライアント様の課題解決に努めています。ここでは、実際のLPO実施事例を2つ紹介するので、参考にしてみてください。
物流・ロジスティクス業界A社様
A社様は、複数のWeb広告媒体で出稿していたものの、広告経由のCVRが低く、費用対効果が悪いことが課題でした。
広告媒体、ターゲティングを精査するとともに、LPにもCVR低下の原因がないかを確認しました。離脱率と問合せにつながるCTAのクリック率に課題があったため、LPOを実施しました。具体的には、広告経由で流入してきたユーザーを繋ぎ止めることを意識したファーストビューへ変更し、フォーム一体型にすることで問合せのハードルを下げる変更を実施しました。
その結果、離脱率の低減、問合せの増加につながり、全体のCVRが100%改善し、同予算内で2倍のCV数を獲得できるようになりました。
商社B様
B社様は、電話利用が多い業界にも関わらず、電話経由での問合せに苦戦していました。問合せの内容を分析したところ、一都三県以外からの問合せがほとんどなく、全国対応しているにも関わらず、お客様に伝わっていないという状況でした。
そこで、LP内に無料電話ボタンを設置するとともに、全国対応であることをわかりやすく伝えるため、対応可能エリアや各地での事例の紹介などコンテンツを拡充しました。その結果、CVRが200%改善し、同予算内で2.5倍の電話問合せ数を獲得できるようになりました。
LPOに必須の3つのツール
LPOを実施する際は、次の3つのツールを必ず使うことになるので、使いこなせるようにしておきましょう。
- アクセス解析ツール
- ヒートマップツール
- ABテストツール
1. アクセス解析ツール
アクセス解析ツールは、Googleが提供している無料ツールGoogle Analytics(GA)を活用しましょう。GAを使うことで、サイトを訪れたユーザーの属性や流入経路だけでなく、サイト内での行動データやコンバージョンの詳細も確認できます。日次、週次など見たい期間を自由に設定できるので、詳細な分析も可能です。
GAは、Google アカウントを作成して、解析したいWebサイトを登録し、トラッキングコードをWebサイトに設定すれば誰でも使えます。LPを新たに作成した際は、必ずデータを取れるよう準備をしておきましょう。
2. ヒートマップツール
ヒートマップツールは、LP上でのユーザーの行動を、サーモグラフィのように色と濃淡で可視化してくれるツールです。ヒートマップツールを使うことで、ユーザーのクリック箇所やスクロール状況、滞在時間などを把握できます。
ユーザーの離脱ポイントを探る際に役立つので、セッションは取れているけれど滞在時間が伸びない、CTAのクリックにつながらないという際に活用してみましょう。
3. ABテストツール
改善策の効果検証にABテストツールは必須です。ABテストツールを使うことで、Aパターン・Bパターンのページを表示するユーザーをランダムに振り分け、成果を比較できます。ABテストは頻繁に実施するので、ABテストツールを使うことで実装と管理を簡単に実施することが可能になります。
まとめ
LPOは広告効果を最大化し、ビジネスを前進させるために非常に重要なマーケティング手法です。LPOに取り組む際は、やみくもに始めるのではなく、必要なタイミングで、手順に沿って進めましょう。コツを掴めばスピーディーにPDCAを回せるようになります。
本記事で紹介した手順と成功のポイントを参考にしたものの、なかなか成果が出ないという方は、専門家に入ってもらうことも検討してみましょう。
当社アクトデザインラボ株式会社では、お客様とコミュニケーションを取りながら、課題を浮き彫りにし、企画・設計〜開発運用までワンストップで支援しています。さまざまな業界・業種のWebマーケティングを支援していますので、ぜひお気軽にお問合せください。