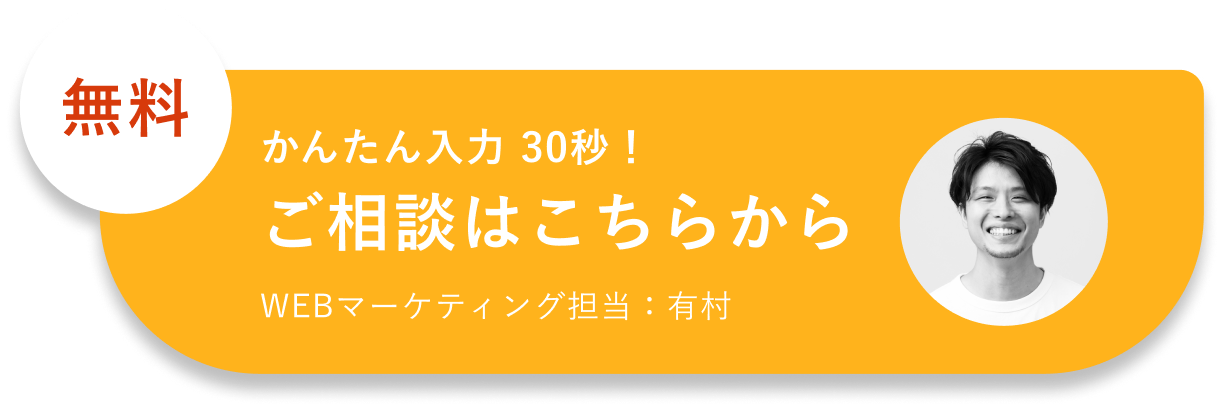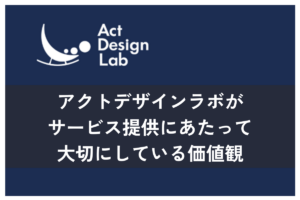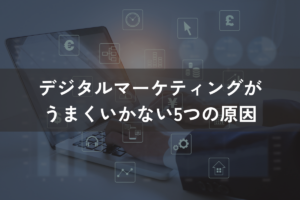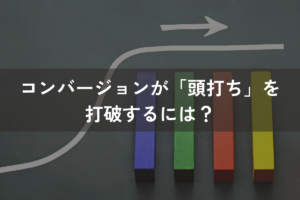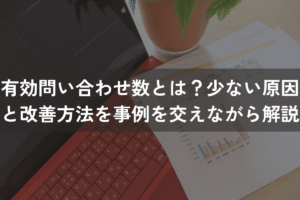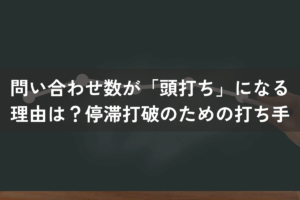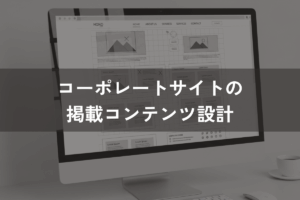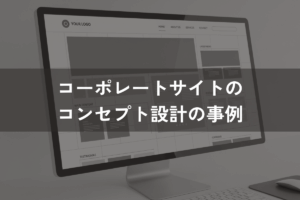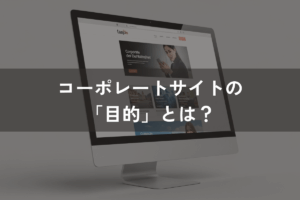LPOとは?その目的と重要性
LPO(Landing Page Optimization)とは、日本語で「ランディングページ最適化」といいます。ランディングページ(LP)をユーザーのニーズに合わせて最適化し、コンバージョン率(CVR)の向上を図るためのマーケティング手法です。もう少し具体的にいえば、LPの訴求力を高めることや、CVまでの導線やストーリーを明確にすることでCVRを高める施策のことです。
LPOの目的
LPOの主な目的は、コンバージョン率(CVR)を上げることです。
LPはWeb広告などをクリックしたユーザーが最初に訪れるページです。そのLPがページの読み込み速度が遅く、なかなか表示されなかったらユーザーは離脱してしまいますし、広告に書いてあったような魅力的な部分がLPをいくら読み込んでも見つからないとしたら、ユーザーは信用を失ってコンバージョン(CV)しません。
そういったCVしない要因をつぶしていくことがLPOの目的です。
LPOの重要性
マーケティングでは、LPやサイトを「受け皿」として表現することがよくあります。そして、LPにはその受け皿に穴が開いていることがしばしばあります。いくら広告で集客を頑張ったとしても、その受け皿に穴がたくさん開いていてザルのようになってしまっては、ユーザーは離脱するばかりで広告費は無駄になってしまいます。
LPOではそういったひとつひとつの穴をふさいで、なるべくユーザーの琴線に触れてCVにつなげるといった重要な役割があります。広告施策を実施していて「どうやってもコンバージョン単価(CPA)が高いまま下がらない」といった場合、LPに原因がある可能性があります。そういった場合はLPを改善しなければ、CPAが大きく改善することはありません。
LPOでCVRが劇的改善!成功事例から学ぶLPO施策
続いては、当社アクトデザインラボが実施したLPOにより、CVRを改善した事例を2つ紹介します。
事例①:フォーム一体型LPの制作・ファーストビューの改善
一つ目は、物流・ロジスティクス系のLP改善事例です。
本件は、Web広告経由でのCVRが低く、CPAが高くなってしまい、費用対効果が悪い状態が続いていました。広告でのCVRの高い広告媒体×ターゲティングに対して予算を寄せるという運用をしつつも、それだけではCPAの大幅な改善は見込めないためLPOを実施しました。
LPは離脱率が高かったため、フォーム一体型LPへの変更とファーストビューの改善施策を行いました。
フォーム一体型LPの最大のメリットは、ユーザーが商品やサービスを購入する際のページ遷移数を大幅に減らせることです。一般的なECサイトでは、商品選択から注文完了まで7段階程度の遷移が必要です。しかし、フォーム一体型LPではこれを短縮でき、ユーザーが感じるストレスを軽減できます。ストレスが軽減され、購入プロセスがスムーズになることで、途中離脱がなくなりCVRの向上が見込めます。
ファーストビュー改善では、ユーザーがサイトに訪れてから最初に目にする部分(ファーストビュー)のコピーやイメージ画像を適切に改善することで、ユーザーの興味を引き、直帰率を大幅に低下させることができます。
この二つを行った結果、改善前と比較して全体のCVRが100%改善し、同予算内で2倍のCV数を獲得できるようになりました。
事例②:電話問い合わせ増加のために行った改善
二つ目は、商社のLP改善事例です。
電話利用が多い業界にも関わらず、電話経由の問合せが思うように獲得できず苦戦していました。日本全国から問い合わせが可能な状態にもかかわらず、一都三県以外の問い合わせがほとんどない状態が続いていました。
改善施策として、東京の基地局の電話番号03の利用をやめ、フリーダイヤル(0120番号)を取得して「無料電話ボタン」の設置を行いました。また、全国対応であることを明示するために、対応可能エリアや実際の事例情報を整理してコンテンツ拡充を行いました。
その結果、改善前と比較して電話問合せCVRが200%改善し、同予算内で2.5倍の問合せ数を獲得できるようになりました。
- 電話番号による理由で首都圏以外が問い合わせ難いイメージを払拭する
- 事例のコンテンツを充実させることでユーザーの信頼を得て問い合わせハードルを下げる
- CTAボタンの最適配置によって最終的にコンバージョンにつなげる
といった複合的な改善により成果を伸ばせた事例です。
事例から見るLPOでCVR改善のための4つのポイント
続いては、具体的な商材事例を参考にしながら、LPOの基本的な考え方やポイントを解説していきます。
- ペルソナやターゲティングに合わせた内容にしてすぐに離脱することを防ぐ
- コンバージョンまでのストーリー(構成)をスムーズに改善する
- まずは簡単なABテストを実施する
- どこで離脱しているかを知るためにツールを使用する
ペルソナやターゲティングに合わせた内容にしてすぐに離脱することを防ぐ
LPがターゲティングやペルソナにマッチしていない場合は、ユーザーがすぐに離脱してしまいます。極端な例として、「プロテイン」の広告を考えてみます。
バーベルを上げている男性のキービジュアルやファーストビューに「筋肉を更にたくましく!」と書かれたLPで、トレーニーやアスリート向けのターゲティングではコンバージョン獲得は好調な状態です。では、獲得を伸ばすための次なる一手として、同じLPで女性のフィットネス層に配信をしたとして、果たしてコンバージョン数は伸びるでしょうか?
答えは明白で、伸びません。いくらバナーで女性向けの明るい感じのバナーを制作したとしても、遷移した先でたくましい男性がバーベルを上げている姿を見たとたんに即離脱してしまうと考えられます。女性ユーザーの滞在時間は短く、離脱率はかなり高くなるでしょう。
これは、トレーニーやアスリートの「鍛えたい・体を大きくしたい」「パフォーマンスを上げたい」などといった需要に対して、女性フィットネスユーザーは「美容・健康」のためにプロテインを飲むといった需要があるためです。
そのため、女性のフィットネス層をターゲティングする場合は女性用のLPを新たに制作し、ファーストビューから女性のビジュアルにし、美容・健康の訴求をしていく必要があります。
このようにLPで(特にファーストビューで)ペルソナやターゲティングがズレていると離脱の原因になってしまいます。バナー広告で訴求している内容とLPの内容が大きくズレている場合はないか、一度見直してみましょう。
コンバージョンまでのストーリー(構成)をスムーズに改善する
LPでは、見せたいコンテンツをただ並べるだけではCVRは高くなりません。並べる順番によってCVRを改善できます。商材によって見せるコンテンツの構成は異なりますが、ユーザーが次の内容を読みたいと思えるような心の動きを想定してLPを作っていく必要があります。
よくある「良いLP」の構成例の一つとしては、次のような構成があります。
- ファーストビューで最も訴求したい部分を伝える
- お悩みなど(こんなお悩みありませんか?など)
- 解決策・効果メリット
- 事例・実例
- お客様の声・実績(UGCやランキング〇位!など)
- クロージング(フォームなど)
ファーストビューを見ただけでコンバージョンするユーザーもいますし、最後まで読み込まないとコンバージョンしないユーザーもいます。あまり知名度のない商品だと「ランキング〇位!!」や「テレビや雑誌で紹介されました!」といった信頼につながる実績を最初のほうに持ってきた方が良い場合もあります。
こういったコンバージョンにつながるまでのストーリー導線を、ユーザーの負担が少なく、次の内容を読みたくなるような順番で配置することも重要なポイントです。
まずは簡単なABテストを実施する
LPOの施策は数多くあります。たとえば、ページの表示速度を改善する場合、本当に必要なコードと不要なコードを見直す必要があるなど、多くの工数がかかります。
そのため、まずは「ボタンのデザインを変える」や「ファーストビューのメインコピーを変える」など簡単に取り組みやすいABテストから実施してみましょう。
一般的に、ひとつの施策の検証には2週間以上の検証期間が必要です。また、どの施策が改善につながったのかの効果検証をするためにも、まとめて2~3個実施するのではなく、実施しやすいものから1つずつ実施していき、その検証期間の間に次の施策の準備を進めると良いでしょう。
どこで離脱しているかを知るためにツールを使用する
LPOでは、CVRが悪いからといって闇雲に改善をしているわけではありません。「このポイントが良くなさそうだ」と当たりをつけて改善を行っています。
その改善ポイントを見つけるために、アクセス解析を実施したり、ヒートマップなどのツールを利用したりします。ツールを使用することで、ユーザーがランディングページ上でどのように行動しているかを詳細に追跡することができます。
クリック数、スクロールの深さ、滞在時間などのデータを収集することで、ユーザーがどの部分で興味を失い離脱しているかを明確に把握できるようになります。
また、ツールを利用することで、A/Bテストや多変量テストを効率的に実施できます。それにより、どのデザインやコンテンツが最も高いCVRを獲得できるか検証することが可能です。これにより、その商材にとって最適なページ構成を見つけることもできるでしょう。
LPO改善に使えるツール3選
続いては、一般的にLPOでよく使用されるツールを3つ紹介します。
- Google Analytics 4(アクセス解析)
- Hotjar(ヒートマップツール)
- Optimizely(ABテストツール)
Google Analytics 4(アクセス解析)
Google Analytics4はGoogleが提供している無料のアクセス解析ツールです。イベントを設定すれば「どのボタンがクリック、タップされていないのか」といったデータが取れるようになったり「どこまでスクロールされているのか」といったデータも取れるようになったりします。
また、ページ内での平均滞在時間やフォームページやCVのサンクスページに遷移した数なども計測でき、離脱ポイントを見つけることができます。
Hotjar(ヒートマップツール)
ヒートマップは、画像で一番見られたり、クリック・タップされていたりする場所をサーモグラフのように暖色で表してくれるツールです。Google Analytics4などといったアクセス解析ツールは使い方をある程度勉強して解析方法を身につける必要がありますが、ヒートマップツールは直感的で誰でも使いやすいツールだといえます。
Hotjarはヒートマップツールでも機能が充実しており、一部無料でも使えるのでここでご紹介します。Hotjarには「レコーディング」という機能があり、ユーザーサイトを訪問してから離脱までのマウスやスクロールの動きを動画で記録することができます。各ユーザーがどこで離脱しているかの実際の細かな動きを確認することができます。
また、「ファネル機能」ではページ毎の離脱率とページ毎の動画を確認することができます。たとえば、LP→フォーム→サンクスページというページ構成になっていたとして、「フォームまで進んだユーザー何%で、そこまで進んだユーザーはどういった動きをしていたのか」という実際のユーザーの動きを動画で確認することができます。
Optimizely(ABテストツール)
Optimizelyは、ABテストをするためのツールです。ABテストとはサイトの一部だけを変えたデザインや訴求でユーザーの反応はどちらがよかったのか検証することです。
たとえば、シンプルなデザインのCTAボタンのほうが良いのか、それでも立体感があって色見もカラフルなCTAボタンの方が良いのかといったボタンのデザインのテストや、キャッチコピーはどちらが良いのか、コンテンツの順番はどの順番が良いのかなどをテストすることができます。
Optimizelyでは、ソースコードをいじることなくABテストのサイクルを回していくことができるためWeb開発者の手間を取らせず、マーケター自身がテストをどんどん回して行くことが可能です。
LPOのよくある失敗例
最後に、LPO施策を実施する際によくある失敗例を紹介します。
- そもそもその商材のCVRが伸びにくい
- ページ外へのリンクが多すぎる
- BtoB商材なのにBtoC向けの構成になっている
- LPO以外の要因でCVRが下がる
そもそもその商材のCVRが伸びにくい
その特性上、CVRがどうしても伸びにくい商材があります。たとえば次のようなものが挙げられます。
- 高額な商材
- ニーズが少ない商材
- 複雑な説明が必要な商材
すべての商材があてはまるというわけではありませんが、これらの商材は、LPOを行っても効果が出にくい場合が多いです。他のマーケティング手法と組み合わせて、ユーザーに対するアプローチを多角的に行うことが重要です。
高額な商材
高額な商品は購入を決断するまでに時間がかかるため、ランディングページ(LP)ではコンバージョン率が低くなる傾向があります。ユーザーは高額商品を購入する前に、他の商品と比較したり、詳細な情報を求めたりすることが多いため、LPだけでは十分な情報提供が難しい場合があります
ニーズが少ない商材
市場での需要が低い商材は、そもそもターゲットユーザーが少ないため、LPOを行っても大きな効果を期待できません。ニッチな市場向けの商品やサービスは、特定のユーザー層にしかアピールできないため、そもそも広範の集客が難しい傾向にあります。
複雑な説明が必要な商材
技術的に複雑な商品やサービスはLPで簡潔に説明することが難しく、ユーザーが理解するまでに時間がかかります。そのため、離脱率が高くなりがちです。こういった商材は、詳細な説明やデモンストレーションが必要な場合が多く、LPだけでは十分な情報提供が難しいことが少なくありません。
ページ外へのリンクが多すぎる
ページ外へのリンクが多いとユーザーの興味が分散し、LPから離脱する可能性が高まります。これにより、CVに至る前にユーザーが他のページに移動してしまうことが多くなります
リンク先でユーザーの興味が別のことに移ってしまい、せっかくサイトに誘導したにも関わらず、ユーザーは興味を失ってLPに戻って来ない可能性が高くなります。
また、LPの目的は特定のアクション(購入、問い合わせ、資料請求など)を促すことです。外部リンクが多いとページの一貫性が損なわれ、ユーザーが混乱する可能性があります。
BtoB商材なのにBtoC向けの構成になっている
BtoBとBtoCでは、ユーザーの行動特性が大きく異なります。
BtoCのLPは、個人消費者が衝動的に購入を決定することを前提に設計されていることが多いです。一方、BtoBのユーザーは、製品やサービスの導入を慎重に検討し、複数の関係者と相談して意思決定を行います。そのため、BtoCの構成では、BtoBユーザーのニーズに応えられず、離脱率が高くなる可能性があります。
また、デザイン面においては、BtoCのLPはターゲット層に合わせた装飾的で感情に訴えるデザインが多いです。一方で、BtoBのLPでは信頼感や安心感を重視したニュートラルなデザインが求められます。BtoCのデザインでは、BtoBユーザーに対して信頼感を与えることが難しく、結果として商談や契約につながりにくくなります。
たとえば、BtoCのLPだと縦に長いLPが主流ですが、BtoCでは簡潔に必要な情報だけをまとめることが多いといえます。BtoBの場合、多くの競合と比較されることが一般であるため、比較されるポイントと独自の機能やメリットをわかりやすく訴求するためです。
LPO以外の要因でCVRが下がる
LPO以外の要因でCVRが下がることがあります。それが、季節的な需要と競合の影響です。
たとえば、脱毛の市場だと6月は夏も近く脱毛の市場が加熱してくる時期です。5月までと比べると広告出稿量が増え、CPMも高くなります。すると、直近でさまざまな広告を見せられるようになったユーザーは、1社の広告を見て決めるのではなく「この前見た広告とどちらが良いのだろう」と比較検討をする可能性が高くなります。また、この増えた需要を確実に刈り取りに行くために、大手クリニックなどは期間限定で価格を下げるなどの大規模なキャンペーンを実施することがあります。
そうすると、1%近かったCVRが半分以下にまで下がってしまうことがあります。このような季節性がありライバルも多い市場だと、LPOとは関係のないCVRの低下が起こることがあります。
まとめ
LPOは、とにかくテストを重ねる地道な作業です。ボタンのデザインや訴求文言などのABテストなど、取り組みやすいところから始めてCVRを上げていくことが重要です。
一時的に良くなったとしても、ユーザー心理の変化やデザイントレンドの変化などでCVRが下がる場合もあり、PDCAサイクルを回していくことが必要です。
今回紹介した事例やポイント以外にも、当社アクトデザインラボ株式会社では、数々のお客様を担当してきて効果のあった施策事例があります。「LPOをやってみたけど効果が上がらなかった」という経験や「LPOをやらないといけないが、何から手をつけたら良いのかわからない」という場合は、ぜひLPOの専門家である我々にお任せください。