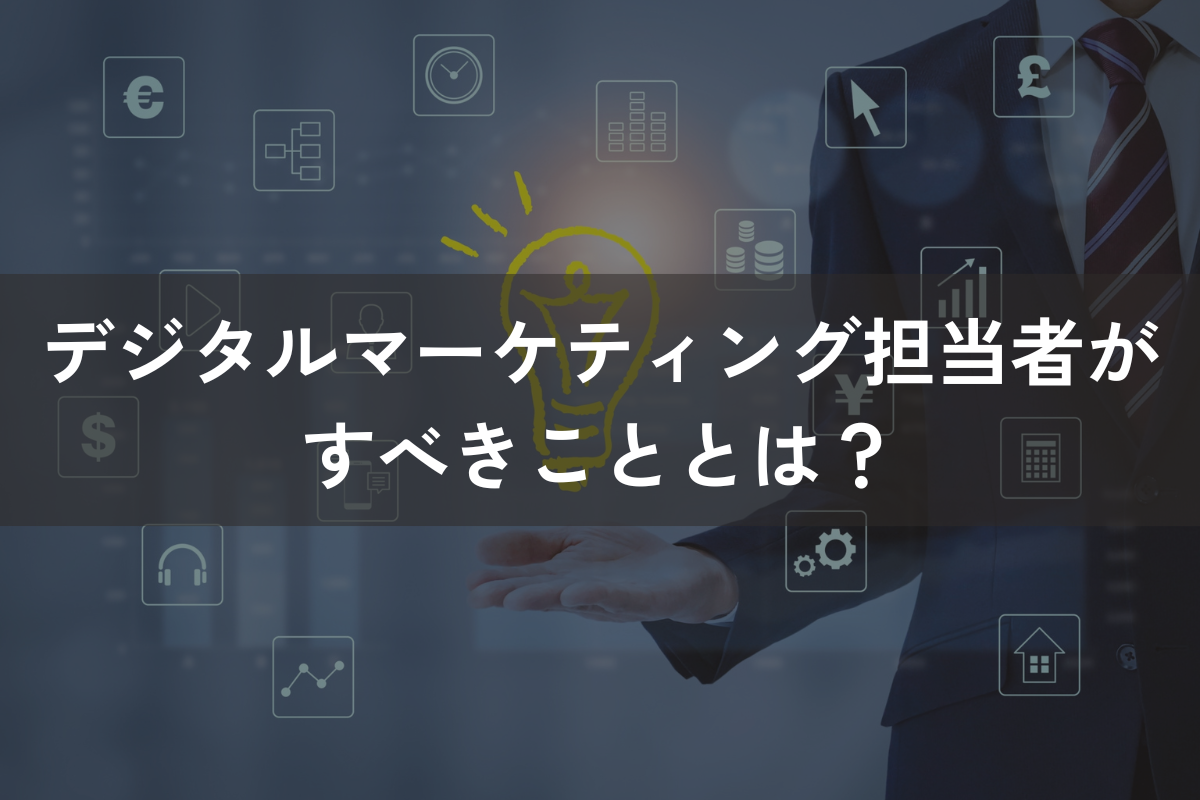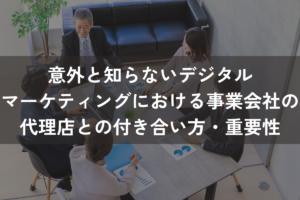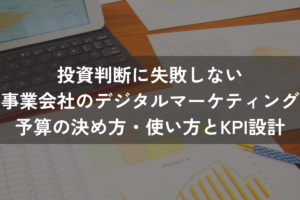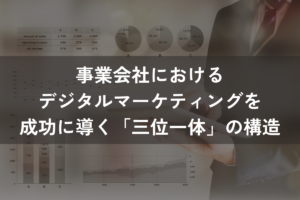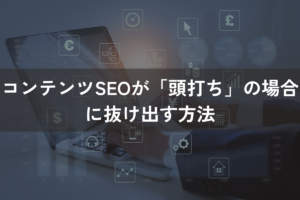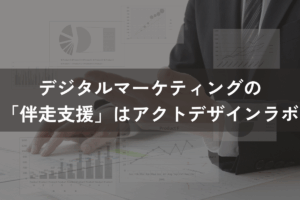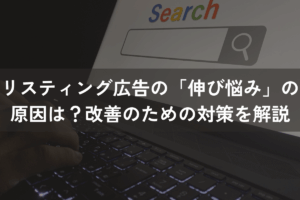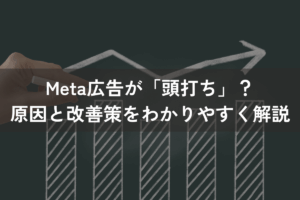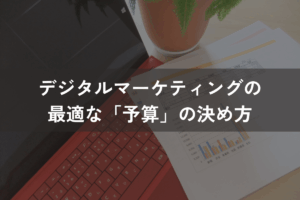「デジタルマーケティングを強化したいが、担当者がいない」「人材不足で十分な施策が進められない」このように悩む企業は少なくありません。担当者不在や知識不足は、多くの企業で成果停滞の大きな要因となっています。そこで今回は、デジタルマーケティングにおいて、担当者不足を補いながら成果を改善するための実践的な方法を解説します。ぜひ最後までご覧ください。
デジタルマーケティング担当者が不在の企業に起こる課題
担当者がいない、または業務が分散している企業では、施策の一貫性や最適化が進まず、社内にノウハウも蓄積されにくくなります。その結果、成果が上がらず競合に後れを取るリスクが高まります。ここでは、デジタルマーケティング担当者の不在により顕在化する、具体的な課題と背景を整理します。
- マーケティング施策の一貫性を欠く
- 広告施策の最適化が進まない
- 社内ノウハウが蓄積しない
マーケティング施策の一貫性を欠く
デジタルマーケティングを個別に進めると、一貫性を欠きやすくなります。担当者が不在の場合、全体の戦略設計が行われていないことが多いためです。各チームが独立して動き、部門間で情報共有が不足する傾向があります。
たとえば、アカウントチームはフォロワー数増加に集中し、口コミチームはインフルエンサー施策だけを重視し、広告チームは獲得系広告のみを運用するといった具合です。このように指標がバラバラになると、部分最適にとどまり施策全体の効果が最大化されません。
全体を統括する責任者がいないことは、組織を縦割りにし、連携不足を深刻化させる要因になります。社内体制が整備されていない企業では、デジタルマーケティングの進捗が遅れる結果につながります。
広告施策の最適化が進まない
担当者が多忙な企業では、広告施策の最適化が進みません。リアルタイムでのデータ収集や分析に時間を割けず、効果測定や改善が滞るためです。さらに、部門間の情報共有が不足すると、非効率な業務環境に陥り、実務に追われて客観的な分析が行えません。
ある調査では、BtoB企業経営者の41.7%が「マーケティング担当者がいない」と回答していることからも、多くの企業で時間不足や施策の停滞が課題となっていることが窺えます。ROIを正確に評価できないまま施策を進めると、誤った予算配分につながり、効果を発揮できない場合があります。
広告のコンバージョン率を維持するには、担当者の配置を含めた体制強化に加え、コスト削減と正しい指標設定を徹底することが不可欠です。
社内ノウハウが蓄積しない
企業のデジタルマーケティングを遅らせる最大の要因は、ノウハウ不足と人材不足です。担当者が不在または知見を持つ人材が不足すると、施策を計画的に進められず社内にノウハウも蓄積されません。
ある調査では、BtoB企業経営者の69.3%が新規リード獲得に課題を抱え、そのうち41.7%が「担当者不在」を理由に挙げています。さらに別の調査では、役職者の59.4%が「知見のある人材が足りない」と回答しており、多くの企業で同様の問題が認識されています。
外部委託に完全に依存してしまう場合、自社に知見が残りにくく将来の戦略立案や人材育成に悪影響を及ぼすため、人材配置を見直しノウハウを蓄積できる体制を整えることが不可欠です。
デジタルマーケティング担当者の機能を外部パートナー活用で補完するメリット
一方、自社だけで成果を出すのは容易ではありません。外部パートナーを上手に活用すれば、最新の知見や専門性を取り入れ、人的リソースやコストの課題を解消できます。ここでは、外部活用のメリットについて解説します。
- 最新の知見と専門性を得られる
- 人材採用・育成コストを削減する
- 実績や事例を確認する
- 成果指標を明確にする
最新の知見と専門性を得られる
デジタルマーケティング活動では、外部の専門家から最新の知見と専門性を得られます。これは、デジタルマーケティングの領域が日々変化し、専門知識の継続的なキャッチアップが求められるためです。
コンサルティング会社や広告代理店、システムインテグレーター、マーケティングツールベンダーなどの支援を受ければ、自社に不足するスキルを効率的に補完できます。特にマーケティング支援会社は多くの案件を扱っており、成功事例や失敗事例を通じて実務的なノウハウを蓄積しています。
これにより、外部パートナーは最新トレンドや効果的な施策に関する知見を迅速に提供でき、自社のスキルアップを支援することが可能です。データ分析や最新技術への対応が遅れるリスクを減らし、競争力の低下を防ぐ効果も期待できます。
人材採用・育成コストを削減する
外部パートナーの活用は、デジタルマーケティングにおける人材採用や育成コストを大幅に削減できます。特に専門性の高い人材の採用は競争が激しく、高額な年収を提示しなければならない場合です。
外部の専門家や副業人材を活用すれば、初期コストを抑えながら優秀な人材を迅速に確保でき、自社でゼロから採用や育成に取り組む時間と費用を節約できます。外部パートナーは企業のマーケティング活動を効率化し、成果向上を実現する重要な協力者です。社内リソース不足を補うために積極的な活用が推奨されます。
実績や事例を確認する
外部パートナーを選定する際は、その会社のデジタルマーケティング実績や成功事例を必ず確認する必要があります。委託したい業務分野で具体的な成果を出しているかどうかは、期待する効果を得る上で極めて重要です。パートナー会社には得意不得意があり、実績のない会社では十分な成果が得られない可能性があります。
たとえば、SNS運用やクリエイティブ制作、Webサイト制作、リスティング広告運用など、依頼内容と近い成功事例を持っているかを確認することがおすすめです。また、提供サービスの範囲が広いかどうかも大切であり、自社ニーズに最適なソリューションを提供できるかを見極める必要があります。
成果指標を明確にする
デジタルマーケティングで成果を出すには、目的と合わせて、成果を測定する指標を明確に定めることが必要です。指標を設けないままでは施策の効果を正しく判断できません。
コンテンツマーケティングに取り組む際も、目標とKPI(重要業績評価指標)を設定し、到達したい状態を数値で表現することが重要です。たとえば、新規リード獲得数を増やすことだけでなく、そのリードが問い合わせや売上にどの程度つながったかを確認できる指標を設けることが求められます。施策の最終ゴールから逆算して指標を設計すれば、投資の成果を正しく見極められます。
自社でデジタルマーケティング担当者を活かすための条件
ただし外部支援を受ける場合でも、社内担当者のパフォーマンスを最大化することは欠かせません。そのためには、役割分担の明確化、経営層の理解、部門を越えた情報共有といった条件が重要です。
- 経営層の理解を得る
- 役割分担を明確にする
- 横断的な情報共有を行う
経営層の理解を得る
デジタルマーケティングで成果を出すには、経営戦略と組織設計が連動していることが不可欠です。経営層が目的やデータ活用の有効性を理解し、積極的に関与すると予算や人材の意思決定が迅速に行われ、現場は方針に沿って施策を進められます。経営層が方向性を示すことで担当者は安心して業務に集中でき、組織全体の優先順位も明確になります。その結果、試行錯誤が戦略と乖離せず、短期間で改善を繰り返せる体制が整います。
経営層と現場の指標にズレがあると、施策は的外れになり、効果を正しく判断できません。この温度差を解消するには、経営層と現場が定期的にミーティングを行い状況をすり合わせることが有効です。
役割分担を明確にする
デジタルマーケティングを内製化するには、責任者と担当者の役割を明確に分けることが欠かせません。担当者が一人で業務を抱え込むと属人化が進み、休暇や退職時に業務が停滞したりノウハウが失われたりする恐れがあります。
これを防ぐには、2名以上の体制を整え、役割やタスクを分担するなどの工夫が必要です。さらに、短納期のLP制作を外部に任せるなど、目的や期間、予算に応じて外部リソースを活用すれば、社内リソースを戦略立案やデータ分析といったコア業務に集中できます。
企業規模や内製化の範囲に合わせて、最適な役割分担と外部活用のバランスを見極めることが重要です。
横断的な情報共有を行う
デジタルマーケティングの成果を最大化するには、マーケティング部門だけでなく営業やIT部門など複数部門との横断的な情報共有と連携強化が欠かせません。情報が部門ごとに散在すると顧客対応の質が下がり、施策の遅延を招きます。
これを防ぐには、「いつ、誰が、どの情報を共有するか」というルールを明確に定め、共有フローを可視化することが必要です。部門横断の定例会議やチャットツール、プロジェクト管理ツールを用いれば、顧客の声を共有したり、問い合わせやタスクを一元管理したりすることができ、施策のタイミングを逃さず迅速な改善につなげられます。
成果を出せるデジタルマーケティング担当者に求められるスキルセット
成果を上げるデジタルマーケティング担当者は、データ分析力、広告や媒体に関する知識、コンテンツ制作力、最新ツールを扱う力をバランス良く備えています。ここでは、これらのスキルがなぜ重要なのかと、その活かし方を掘り下げます。
- データ分析力を高める
- 広告・媒体知識を習得する
- コンテンツ制作力を磨く
- 最新ツールを活用する
データ分析力を高める
デジタルマーケティングで成果を出すには、数字やデータを活用した意思決定の仕組みを確立することが不可欠です。具体的には、Webサイトのアクセス数やコンバージョン率、顧客獲得コスト、SNSのエンゲージメント率を把握し、施策の検証や改善に反映させます。
データ分析は顧客の行動パターン理解に直結し、ターゲット選定やチャネルの判断に役立つものです。担当者にはGoogle Analyticsなどの解析ツールやBIツールを使いこなし、データを整理・分析・活用する力が求められます。データに基づいてPDCAサイクルを回すことで効率的に施策を展開でき、事業成長を加速させることが可能です。
広告・媒体知識を習得する
デジタルマーケティングには、SEOやWeb広告(リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告、動画広告)、SNS運用、コンテンツマーケティングなど多くの手法があります。各媒体の特性や活用法を理解し、経営戦略や事業課題に応じて最適化することが必要です。
ターゲットのニーズを把握し、適切な媒体を選んで宣伝方法を実施すれば、高い効果を期待できます。さらに、顧客の購買プロセスに合わせてコンテンツを届けることで、問い合わせの質を高められます。
知識が不足している場合は外部コンサルタントや専用ツールを活用し、効率的にスキルを補う方法も有効です。
コンテンツ制作力を磨く
デジタルマーケティングで成果を上げるには、価値あるコンテンツを制作する力が不可欠です。ユーザーの悩みや疑問を把握し、それに応える情報を提供すれば効果的です。目を引くコピーや魅力的な企画を構想する発想力に加え、図表やイラストを使い情報を視覚的に整理する力も求められます。
単に量を重ねた低水準のコンテンツでは成果につながりません。ユーザー目線で最適化された情報を発信し続けることで顧客満足度やブランドへの信頼を高め、結果として売上やリード獲得に結びつきます。
最新ツールを活用する
デジタルマーケティングを効率的に進めるには、最適なツールの利用が欠かせません。AIやビッグデータを扱う分析ツール、SNS管理ツール、メールマーケティングを実行する仕組みを活用し、最新技術を駆使した販促を行います。特にGoogle AnalyticsやGoogleキーワードプランナーといったツールは、現状把握と改善の基盤として重要です。
またMA(マーケティングオートメーション)を導入すれば、リード獲得や育成、顧客リストの一元管理、作業の自動化が可能となり、活動全体の効率を大幅に高められます。さらにCMSを導入することで、専門知識がなくてもコンテンツを容易に追加や修正でき、継続的な発信体制を維持できます。
デジタルマーケティング担当者が成果を出す施策の進め方
デジタル化の進展で顧客行動が複雑化し競争が激化する中、計画的な施策設計の重要性は一層高まっています。成果を出すには、ターゲット設定からチャネル戦略設計、テストと改善、定量評価までを一貫して進めることが欠かせません。ここでは、その流れを具体的に解説します。
- ターゲットを明確にする
- チャネルごとに戦略を設計する
- テストと改善を繰り返す
- 成果を定量的に評価する
ターゲットを明確にする
現代のマーケティングでは、消費者の行動やニーズが多様化しているため、担当者にはターゲットを細分化しセグメントごとに戦略を立てることが求められます。年齢や性別だけでなく、行動パターンや価値観、課題意識までを含めた詳細な人物像、いわゆる「ペルソナ」を設定することが重要です。
ペルソナ設定により顧客の悩みや疑問を理解でき、的確なアプローチが可能です。たとえば、40代のママさん向け製品なら、共感を得られる投稿や企画を立案でき、顧客獲得につながります。データを基盤にした体系的なペルソナ作成は、カスタマージャーニー設計を支える基盤となり施策の精度を高めます。
チャネルごとに戦略を設計する
デジタルマーケティングでは、Webサイトに加えてSNS(Instagram、 Xなど)、Eメール、アプリ、広告(リスティング、ディスプレイ、SNS広告、動画広告)を統合的に活用する必要があります。ECサイトやオフライン店舗とこれらのチャネルを連携させ、一貫した施策を設計することが重要です。
たとえば、アカウントチームがファネルを意識した投稿を行い、口コミチームが広告転用を見据えてインフルエンサー施策を実施するなど、連携すれば相乗効果を得られます。
情報を点ではなく網のように張り巡らせ、認知から決定までの各段階に適したコンテンツ(SEO記事や事例、ホワイトペーパーなど)を配置し、最適なチャネルで届けることで質の高い問い合わせに結びつきます。
テストと改善を繰り返す
デジタルマーケティングは、企画から実施、成果計測、分析、改善を繰り返すPDCAサイクルを継続することが重要です。リアルタイムのデータ分析により、効果が高い施策は迅速に改善し、効果が低ければ即座に見直せます。
すべての施策が成功するわけではないため、A/Bテストを使ってLPやメールのクリエイティブを最適化し、月次レビューで改善を反映する仕組みが必要です。仮説検証を続ける姿勢と、失敗から学んで知見を蓄積する姿勢が、長期的な成果を生み出す組織を築く力になります。
成果を定量的に評価する
デジタルマーケティングでは、購入者数やサイト滞在時間、広告クリック数、コンバージョン率を数値化して分析できます。施策実施後は、適切な効果測定とデータ収集が不可欠です。KPIの達成度や顧客獲得コスト、ROIを評価し改善することが極めて重要です。
たとえば、Google Analyticsでチャネル別のCVRを測定し、高成果のチャネルに投資を集中させれば、限られたリソースを効率的に配分できます。さらに、BIツールで分析結果をレポート化し、経営陣と成果を共有すれば、投資対効果を明確に示せる担当者として信頼を得られます。
外部活用とデジタルマーケティング担当者の連携によるハイブリッド型運用
社内だけではデジタル施策に追いつかない部分がある場合、たとえば戦略は外部、実行は内製といった形で外部パートナーと社内担当者が役割を分担する「ハイブリッド型」運用を行い、効率と成果の両立を目指すことができます。ここでは、そんなハイブリッド型運用のパターンと導入のポイントを解説します。
- 戦略設計は外部、実行は内製にする
- 一部施策のみ外部委託する
- 定期的に外部評価を受ける
戦略設計は外部、実行は内製にする
外部パートナーによる戦略設計と社内での実行を組み合わせるハイブリッド型運用は、成果を最大化する仕組みを実現できます。自社の担当者は全体をディレクションしながら、Webサイトの戦略設計やLP制作など専門性の高い作業を外部に委託することでバランスの取れた運用が可能です。
実行すべきことが明確でも人手が不足する場合には、外部企業にリソース支援を依頼できるため、限られた人材を最適に活用できます。さらに、人材育成と外部調達を組み合わせることで、初期投資や育成コストを補いつつ最新知識を取り入れ、実践を通じてノウハウを社内に蓄積でき、競争力を高められます。
一部施策のみ外部委託する
デジタルマーケティングの範囲は広く、すべてを社内担当者だけで担うのは困難な企業が多いのが現状です。この課題に対して外部委託を一部導入すると、各ベンダーの専門領域を活かした役割分担が可能になります。たとえば、コンサルティング会社は戦略立案やKPI設計を支援し、広告代理店はキャンペーンの企画と実行、ツールベンダーは導入と設定を担当します。
さらに、SNS運用、SEOやコンテンツ施策、データ分析などは外部活用との相性が良く、質の高い成果に直結します。特にBtoB企業で新規リード獲得が課題となる場合、外部マーケターの知見は有効です。
こうしたタスクを外部に任せれば、社内担当者は戦略的判断やブランド理解を基にした施策に集中できます。
定期的に外部評価を受ける
デジタルマーケティングで市場や顧客の変化に対応し成果を高めるには、PDCAサイクルを継続的に回せる体制が必須です。この改善プロセスにおいて外部専門家による定期的な評価と分析は極めて重要です。たとえば、マーケティングミックスモデリング(MMM)を用いれば施策の事業貢献度を数値で把握し、ROIを可視化できます。
外部パートナーが施策の目的や結果を定期的に報告すれば、社内にノウハウが蓄積され、業務の不透明化を防ぎつつ改善策を導き出せます。こうした仕組みにより、社内担当者は日々の運用から解放され、戦略的な意思決定や事業への貢献に集中できる環境を整えることが可能です。
デジタルマーケティング担当者との連携による成功事例
最後に、社内担当者の業務知識とアクトデザインラボのマーケティング専門性を組み合わせ、具体的な成果を生み出した事例を紹介します。両者の役割を明確に分担し、継続的な改善を重ねることで成果を高めた実例です。
ケース1:商社A社でのSEM集客体制構築
商社A社では、多様な商材の中から収益性の高い分野に注力し、SEMを活用した安定的な集客の実現を支援しました。社内担当者が持つ商材知識とアクトデザインラボの戦略設計・実行支援力を組み合わせ成果を得た事例です。
具体的には、まず集客目的を明確化した上でビジネスモデルや市場・競合の調査を行い、注力商材を特定しました。その後、社内知見を活かした記事コンテンツと、外部スタッフが制作した広告用LPをアクトデザインラボのチームで制作・展開し、PDCAを継続的に回しました。
加えて、成果チェックできるダッシュボードや社内の意思決定プロセスを整備したことも功を奏し、SEM経由での問合せ獲得が安定し、持続可能な仕組みの構築に成功しています。
ケース2:物流B社でのSEM集客体制構築
この事例は、物流B社で法人向け物流サービスの登録事業者数を増やすことを目的に、Web集客戦略の立案から実行までを支援した取り組みです。はじめに、物流会社へのヒアリングを行い、登録数が伸び悩んでいることや新規獲得効率が低いことなど、現場が抱える課題を明確にしました。
これらの課題に対応するため、過去の施策実績を丁寧に分析し、最適なメディアプランと予算配分を設計しました。さらに、既存顧客データをもとに長期利用者の特徴を抽出し、その知見をターゲティングの精度向上やコンテンツの訴求軸の見直しに活用しています。
併せて、導入時の心理的ハードルを下げるべく、トライアルの条件を再設計し、ユーザーが利用を開始しやすい環境を整えました。こうした施策を段階的に実行し、検証と改善を繰り返した結果、予算を据え置いたまま、従来の約3倍にあたる登録事業者数の獲得へとつなげることができました。
ケース3:人材会社C社におけるWebマーケティング支援
本事例は人材会社C社で、Webマーケティング活用を通じて、問い合わせ数の増加と事業成長を支援した取り組みです。まず、人材会社へのヒアリングを実施し、複数サービスにまたがる戦略の不在や、Web経由の問い合わせ数が伸び悩んでいることを主な課題として特定しました。
そこで、優先的に取り組むべきサービスを明確にするため、ビジネスモデルやサービス内容の把握に加えて、市場・競合の調査を実施しました。その上で、Web集客や制作の専門メンバーをアサインし、問い合わせ数の向上に向けた戦略の立案と実行を進めています。
まずは特定サービスに絞って施策を実行し、成果を確認した後、他サービスにも横展開を行いました。結果として、Web経由の月間問い合わせ数は3ヶ月で従来比10倍以上に増加し、他事業への展開によってさらに2.5倍の伸びを実現しました。
まとめ
デジタルマーケティングで成果を出すには、社内担当者の知見と外部の専門力を組み合わせることが不可欠です。アクトデザインラボでは、戦略設計から実行支援まで一貫してサポートし、改善を重ねながら成果創出を実現しています。
さらにデータ分析や最新ツール活用も組み合わせ、継続的に成果を高める体制づくりを支援しています。自社だけで限界を感じる場合は、お気軽にご相談ください。