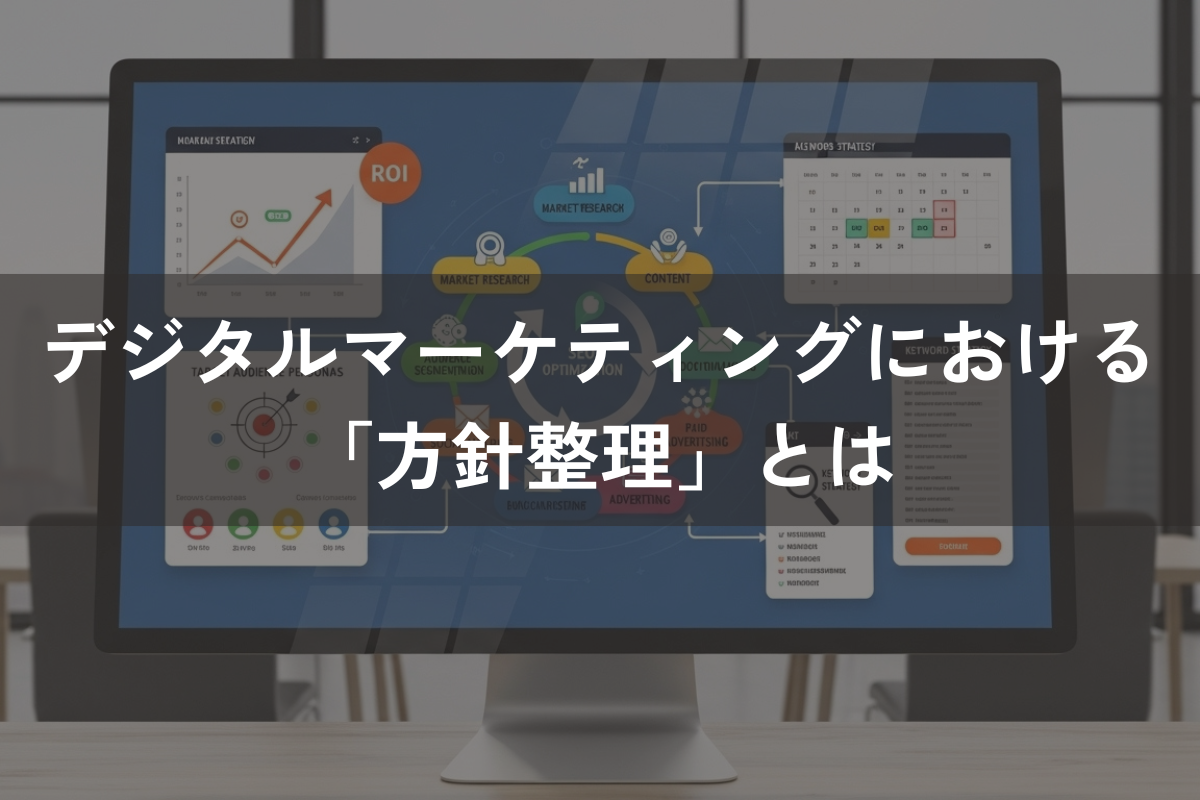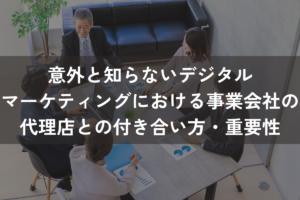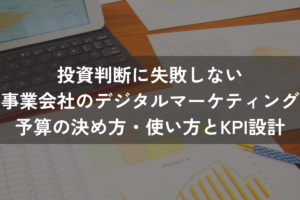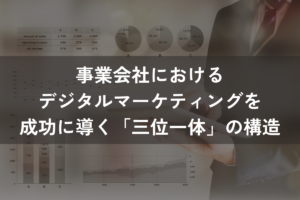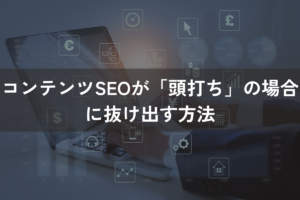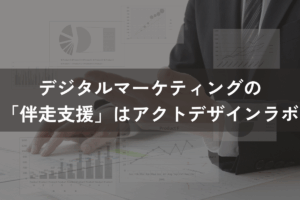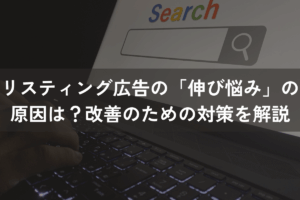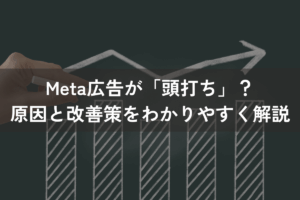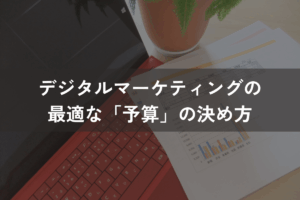「広告を出しているのに成果が安定しない」「施策を実行しても思うように数字が伸びない」こうした悩みを抱える企業は少なくありません。その背景には目的の曖昧さや手段の目的化、複雑な実行設計といった課題があります。
成果を持続的に高めるには、全体の方針を整理し、戦略から実行、改善までを一貫して進める仕組みを整えることが欠かせません。今回は、デジタルマーケティング方針整理の意義や進め方、さらに成功事例を紹介します。
デジタルマーケティングの「方針整理」は成果安定のカギ
施策の成果が安定しない原因は、目的の曖昧さ、手段の目的化、そして複雑な実行設計です。目的が不明確であれば施策は場当たり的になり、手段そのものが目的化すれば全体戦略との整合が失われ、さらに設計が複雑化することで運用が混乱し成果も揺らぎやすくなります。方針整理はこれらの課題を解消し、戦略を長期的に機能させるための土台を構築します。
成果がぶれる企業に共通する3つの課題
デジタルマーケティングで成果が不安定な企業には、3つの共通課題があります。これらが施策の方向性を見失わせ、非効率な運用を招くことで成果の揺らぎにつながります。
- 手段の目的化
- 実行設計の複雑さ
- 膨大な作業量
こうした課題を解決することが、成果を安定させるための第一歩となります。
手段の目的化
まず、「手段の目的化」です。現場ではオウンドメディアやSNSといった施策が、本来のゴールではなく目的そのものになってしまうケースが見られます。
実行設計の複雑さ
次に「実行設計の複雑さ」が挙げられます。抽象的な目的を具体的な施策やシステムに落とし込む過程は難解で、技術や運用の整合を取る作業が煩雑になりがちです。
膨大な作業量
最後に「膨大な作業量」です。やるべきことが多い中で、限られた予算や人員では優先順位を定められず、小規模な試行すら迷走する場合があります。
方針整理によって得られる5つの効果
方針を整理すれば戦略の精度が高まり、中長期的な成果を最大化できます。なぜなら、施策の全体像を把握しやすくなり、効率的な実行が可能になるからです。方針整理によって企業が具体的に得られるメリットには、次の5つがあります。
- 全体戦略の設計によって施策が部分最適に陥らず、持続的な効果を生み出せます。
- オンライン・オフラインを問わず顧客データや販売履歴、行動履歴を活用することで、事実に基づいた正確な施策立案が実現します。
- 成果をリアルタイムで確認し迅速に改善できるため、費用対効果が向上します。
- 活用できるチャネルが増え、これまで接触できなかった層へのアプローチが可能となります。
- 顧客一人ひとりの情報を基にレコメンデーションやリターゲティング広告、パーソナライズメールを実施でき、顧客満足度とロイヤルティの向上を実現します。
成功事例に見る方針整理のインパクト
方針整理はデジタルマーケティングの成果に大きな影響を与えます。実際に多くの成功企業が、戦略的な方針整理に基づいた施策で成果を上げています。
【方針整理で成功した事例】
| 企業 | 方針整理した内容 | 成果 |
|---|---|---|
| コロナ禍で顧客接点が減少した企業A社 | サイト刷新・広告出稿・MA・オンライン施策を活用 | セッション数・CV数・売上の大幅向上 |
| 高額製品を扱う企業B社 | SEO強化・広告運用・サイト改修を実施 | 集客改善+CV改善、利益率向上 |
| 営業主体の企業C社 | MAを中心に据えた施策に切り替え | リード獲得数の拡大 |
| D2C戦略を導入した企業D社 | 自社ECサイトを強化 | ECモールを超える売上を達成 |
| 会員管理ツールを導入した企業E社 | 登録・管理を見直し効率化 | 登録者倍増+コスト削減 |
| オウンドメディアを強化した企業F社 | オウンドメディアのコンテンツ拡充と最適化 | PVと問い合わせ件数を大幅増加 |
デジタルマーケティング方針整理のプロセス全体像
整理したデジタルマーケティング方針を成果につなげるには、現状把握から改善までを体系的に進める必要があります。課題抽出、戦略立案、実行計画、評価改善を連動させることで、施策は持続的な効果を発揮します。
現状把握から課題抽出までの流れ
デジタルマーケティングの戦略立案は、現状把握と課題抽出から始まります。
まず、Webサイト、SEO、SNS、広告といった全施策を整理し、PVや訪問者数、直帰率などのデータから強みと弱みを把握することが重要です。
次に、課題を分類・構造化し、マーケティング部門と事業部門の知見を合わせ、SWOT分析や3C分析といったフレームワークを用いて体系的に整理します。このプロセスを通じて、具体的に解決すべき課題が明確になります。
戦略立案と方針策定のステップ
課題を把握した後は、デジタルマーケティングの戦略立案に進みます。
まず、CVR改善や新規問い合わせ増加など、数値で測定可能な目的を設定することが出発点です。次にSTP分析で市場と自社の立ち位置を確認し、ペルソナとカスタマージャーニーによって顧客行動を可視化します。
そして、最終目標となるKGIとKPIを定め、具体的な数値計画へ落とし込みます。これらのステップを経ることで、成果に直結する明確な方針が策定される流れです。
実行計画への落とし込み方
戦略とKPIを設定した後は、行動計画に落とし込みます。
目的や現状、リソースを踏まえ、Web広告、SEO、コンテンツ、SNS、MAなど優先度の高い施策を選定して組み合わせることが重要です。これにより、限られたリソースで最大の効果を狙うことが可能です。さらに月単位・週単位の数値目標を設定し、複数チャネルの相乗効果を意識して実行します。
計画的な運用体制を構築することで、安定した成果を支える基盤が整います。
評価と改善を組み込む仕組みづくり
デジタルマーケティングの成果を安定させるには、評価と改善を組み込む仕組みづくりが欠かせません。施策実行後は、アクセス解析ツール(GA4)やMAツールを用いて効果をリアルタイムで測定し、PDCAサイクルを高速で回して改善を積み重ねることが求められます。
KPIは定期的にモニタリングを行い、数値変化の要因を多角的に分析する仕組みを整えます。さらに、営業やカスタマーサクセスからの定性情報を取り入れ、現場の実態を反映させることが重要です。こうした仕組みによって施策改善が実現し、持続的な成果へと確実につながります。
デジタルマーケティングにおける方針整理で押さえるべき戦略設計の要点
整理したデジタルマーケティングの方針を実行性あるものにするには、ブランド軸や価値提案を明確化することから始めます。ターゲット、メッセージ、チャネルを統一的に設計することで、顧客接点の質と量を最大化することが可能です。さらに、一貫性のある戦略は社内外での共通理解を生み、持続的な成果へ直結する基盤となります。ここでは、デジタルマーケティングにおける方針整理で押さえるべき戦略設計のポイントを解説します。
- ブランド軸と価値提案を定める
- ターゲットセグメントを精緻に設定する
- メッセージとクリエイティブの方向性を統一する
- チャネル戦略と予算配分を明確にする
ブランド軸と価値提案を定める
デジタルマーケティングの戦略設計は、企業が提供する価値を明確にし、ブランドの立ち位置を定めることから始まります。見込み顧客のニーズを深く理解し、そのニーズに応える価値あるコンテンツを適切なタイミングで届けることが重要です。
これにより顧客との信頼関係を築き、購買へと結びつけられます。さらに、動画やSNSなどのリッチコンテンツを活用してブランドの魅力を直感的に伝えることで、ファンを増やし、ブランド力を高める効果を得られます。
ターゲットセグメントを精緻に設定する
デジタルマーケティングでは、顧客像を具体的に描き、ニーズを深く理解することが欠かせません。性別や年齢、年収といった基本属性に加え、勤務先や趣味、行動パターンまで詳細に設定し、リアルなペルソナを構築します。
その上で、ペルソナが顧客となるまでの行動プロセスを可視化したカスタマージャーニーを作成し、認知から購買までの流れを把握することが重要です。これにより、顧客との最適な接点やコミュニケーションのタイミングを明確にできる構造が整います。
メッセージとクリエイティブの方向性を統一する
ターゲットに響く一貫したメッセージとクリエイティブの設計は、成功に直結する要素です。読み手が求める「答え」を的確に提示し、関連キーワードを文章や見出しに自然に盛り込むことが重要です。
また、ペルソナの課題や価値観を反映させ、見出しを見ただけで内容が伝わる構成にすることでユーザーの離脱を防ぎます。加えて、難しい漢字を避けて平易な言葉を使い、箇条書きを取り入れることで、誰にとっても読みやすい文になります。
チャネル戦略と予算配分を明確にする
顧客接点が複雑化する現代においては、複数チャネルを組み合わせた戦略と柔軟な予算配分が必要です。オンラインとオフラインを統合する「オムニチャネル」の発想に基づき、顧客がシームレスに購買体験を得られる仕組みを構築します。
各施策の特性を活かしながら相乗効果を狙い、ROASやCPAといった指標を基準に、成果に応じて予算を再配分する体制を整えることが費用対効果の最大化に直結します。
整理したデジタルマーケティングの方針を実行に移すための施策設計と優先順位付け
限られたリソースの中で成果を最大化するには、施策を時系列で整理し、さらに明確な優先順位を設定することが不可欠です。短期・中期・長期の施策をバランスよく組み合わせ、各段階に適したKPIを設定することで、限られた人員や予算でも効率的な進行が可能になります。こうした仕組みによって実行精度を高め、成果を安定的に積み上げられます。ここでは、整理したデジタルマーケティングの方針を実行に移すための施策設計について解説します。
- 施策を短期・中期・長期で整理する
- 限られたリソースで最大効果を出す優先順位をつける
- KPIとモニタリング体制を整備する
施策を短期・中期・長期で整理する
デジタルマーケティングの施策は、効果が現れる時期や目的に応じて短期・中期・長期に整理することが重要です。
短期施策にはリスティング広告やSNS広告があり、即効性が高く特定のユーザー層に素早く成果を届けられる手段です。たとえば、Twitter広告で新規顧客を2倍にし、CPAを削減した事例があります。
中期施策ではコンテンツマーケティングやSEOを通じて良質な記事を継続的に提供し、検索流入を増やして集客基盤を形成します。
長期施策ではMAやCRMを活用し、顧客データを一元化して最適なコミュニケーションを自動化し、LTV向上へつなげます。
さらに、オンラインとオフラインを統合する「オムニチャネル」戦略も、顧客体験の質を高める有効な取り組みです。
限られたリソースで最大効果を出す優先順位をつける
限られた予算や人員、時間で成果を最大化するには、施策の優先順位を明確にすることが欠かせません。多くの企業は予算を均等に配分したり流行の手法に依存したりして、費用対効果を損ねています。
これを避けるには、まず目的と成果指標を明確化し、過去データを分析して改善仮説を立てることが必要です。さらに、ROASやCPAなどの指標を用い、投資すべき施策を定量的に判断します。
効果が薄い取り組みには固執せず、当初の仮説と異なる結果が出ればサンクコストを切り捨て、柔軟に方向を修正する姿勢が求められます。グロースハックの考え方でも、課題の特定と優先度付けを行い、仮説検証と改善を繰り返す姿勢が重視されます。
流行に流されず、各施策のメリットとデメリットを理解したうえで、事業目標に最適な手段を選ぶことが大切です。
KPIとモニタリング体制を整備する
施策の効果を正しく評価し、継続的に改善するには、KPI設定と計測環境の整備が必要です。
まずKGI(重要目標達成指標)から逆算し、達成すべきKPI(重要業績評価指標)を数値化し、期限を設けることが重要です。特に認知、リード獲得、関係性の段階ごとに適切な指標を設定します。
KPIは単なる数値ではなく、効果分析や改善につながる設計が必要です。設定にはSMART原則(具体的・計測可能・達成可能・目標と関連・期限付き)を用いると評価が容易になります。さらに、GA4やMA、CRMを活用して進捗を把握し、週次や月次で定期的に確認します。これにより、目標達成度や課題を的確に分析でき、改善アクションに反映できます。
デジタルマーケティングでの社内合意形成と外部パートナー活用の成功条件
整理した方針を全社に浸透させ、外部リソースと結びつけるには、経営層と現場の認識を一致させ、情報共有と意思決定を効率化することが欠かせません。外部パートナーの選定は、自社課題と市場変化の双方に適合させる必要があります。ここでは、デジタルマーケティングでの社内合意形成と外部パートナー活用の成功ポイントを解説します・
- 経営層と現場の認識を一致させる
- 社内での情報共有と意思決定プロセスを最適化する
- 信頼できる外部パートナーを選定する
経営層と現場の認識を一致させる
デジタルマーケティングを成功させるには、経営層と現場が同じ方向を向き、共通の目標に進む体制が必要です。経営層がデータ活用を理解し、トップダウンで変革を推進して全社的な仕組みを整えることが重要です。KGIから逆算して目的とKPIを明確にし、経営戦略と連動させれば共通認識が形成され協力も得やすくなります。
ただし、経営層が活用方法を理解していなければ施策は進みません。成果や事例を「見える化」し、レポートや勉強会で共通言語を持つ環境を作ることが効果的です。
さらに、各部門がKPIを連携させれば、情報断絶を防ぎ全体最適につながります。協力を求める際は役割とメリットを示し、利害調整を行うことが求められます。
社内での情報共有と意思決定プロセスを最適化する
整理したデジタルマーケティングの方針を実行に移すには、部門横断の連携と情報共有の仕組みが重要です。マーケティング、営業、カスタマーサクセスが協力し、KPIの整合性を確保することが求められます。CRMやSFAを使って顧客情報を共有すれば、部門間の断絶を防ぎ、一貫性ある指標管理が可能になります。
さらに、DMPを導入すればWeb行動データやCRM情報を統合し、購買ジャーニーを横断的に分析できます。これにより変化に迅速に対応でき、施策調整の精度も高まります。
定期的に会議で進捗と課題を共有し、意思決定を明確化すれば調整は円滑に進めることができます。教育や研修でデジタル理解を高めることも、施策の質を底上げする基盤になります。
信頼できる外部パートナーを選定する
整理したデジタルマーケティングの方針を実行に移すには、自社リソースだけでなく外部の力を取り入れる判断が重要です。全領域を自社で担うのは難しく、特に広告運用は仕様変更やトレンド対応が多いため、多くの企業が専門パートナーと協業しています。市場や技術の変化に対応するには、専門性と経験を備えたパートナーを選ぶことが必要です。
選定では「ランキング」や「価格」といった基準に依存せず、自社の目標や課題に合う支援を行えるかを実績から見極めましょう。戦略立案から施策実行、改善まで伴走するパートナーなら短期間で立ち上げられ、社内リソースを戦略や企画に集中できます。
将来的な内製化を見据え、データ基盤や人材育成を含むコンサルティングを組み合わせる方法も有効です。
デジタルマーケティングの方針を継続的に整理・改善するための運用体制
整理した方針を持続的に成果につなげるには、データ活用と改善指標を明確にし、PDCAを継続的に回す仕組みが重要です。市場や顧客の変化に対応するためには、短いサイクルで現状を分析し改善を繰り返すことが求められます。
こうした体制を構築することで、施策を常に最適化し、方針を実行性あるものとして維持できます。ここでは、デジタルマーケティングの方針を継続的に整理・改善するためのポイントを解説します。
- PDCAを回すためのデータ活用を行う
- 改善指標とモニタリングサイクルを設定する
PDCAを回すためのデータ活用を行う
デジタルマーケティングの方針整理を形骸化させないためには、PDCAサイクルの中でデータを継続的に活用することが重要です。
施策実行後は広告管理画面やアクセス解析ツールを用い、リーチ数、クリック率、コンバージョン数といった効果を定量的に測定し、現状を数値で評価します。また、CRMやSFAで収集した顧客情報、POSデータなどもDMPで統合・管理し、形式を揃えて分析することが大切です。
明らかになった課題に基づき、クリエイティブや配信設定、ランディングページを改善し、PDCAを高速で回すことで施策の成功率を高められます。最終的には、データドリブンな意思決定へと結びつきます。
改善指標とモニタリングサイクルを設定する
デジタルマーケティングで継続的な改善を実現するには、適切な指標設定とモニタリング体制が必要です。
まず、KGI(重要目標達成指標)から逆算し、KSF(重要成功要因)とKPI(重要業績評価指標)を連動させることで、各施策が事業目標にどう貢献するかを明確にできます。KGIとKPIに基づき、週次や月次で成果をモニタリングし、ギャップを分析して改善点を特定することが大切です。
また、PDRサイクルのように短い間隔で効果測定と実行を繰り返すことで、市場やユーザーニーズの変化に迅速に対応でき、チーム全体で共有・活用する体制を整えられます。その結果、モチベーションを維持しながら改善を継続的に進めることが可能です。
デジタルマーケティングの方針整理実施の成功事例
これまでデジタルマーケティング方針整理の重要性や具体的な進め方を解説してきました。最後に、当社アクトデザインラボが支援した企業の成功事例を紹介し、実際にどのように成果へとつながったのかを具体的にお伝えします。
ケース1.商社におけるSEM集客体制の構築
商社A社では、成果を安定させるためにデジタルマーケティングの方針整理に本格的に取り組みました。
最初のステップは「どの商材を軸に問い合わせ獲得を目指すのか」という目的を明確にすることです。ビジネスモデルの棚卸しや市場・競合調査を徹底し、注力すべき商材を特定しました。
次に、SEOメディアを含むSEM集客体制を再設計し、社内の専門メンバーと連携して記事コンテンツや広告用LPを制作しました。運用開始後はPDCAを継続的に回し、SEM経由で安定した問い合わせを得る成果につながっています。
また、業務オペレーションや社内外の役割分担を整理し、成果ダッシュボードと意思決定プロセスを明確化することで、具体的な施策を迅速に推進できる環境を維持しています。
ケース2.物流業における法人向けサービスの登録事業社数拡大
物流業界のB社では、法人向けサービスの登録事業社数を拡大することを目的に、Web集客の戦略立案と実行支援に取り組みました。
方針整理の第一歩は過去施策の分析で、メディアプランや予算イメージ、配信シミュレーションを明確にしています。そのうえで、既存顧客データを活用し、長期的に利用する事業社の特徴を抽出しました。これをターゲティングや訴求軸に反映した結果、過去と同水準の予算内で登録事業社数を約3倍に増やす成果につながっています。
また、狙うセグメントを絞り込み、配信メディアやコンテンツの訴求軸を整理して検証と改善を繰り返しました。加えて、トライアルのルールを整備し、導入ハードルを下げたことで、継続利用を促す仕組みが構築されています。
ケース3.人材紹介業におけるWeb経由問合せ数の大幅増加
人材紹介会社C社では、事業成長に直結するWebマーケティングの方針整理を進めました。
まず、優先的に着手すべきサービスを選定するために、ビジネスモデル整理やサービス理解、マーケット調査、競合調査を実施しています。そのうえで、Web集客と制作の専門知識を持つメンバーを配置し、問い合わせ数向上を目指した戦略立案と実行支援を行いました。
特定サービスで成果が確認されると、他サービスへの横展開を進め、施策全体のスケールを拡大しています。取り組み開始から約3ヶ月でWeb経由の月間問い合わせ数は従来比で10倍以上となり、その後の横展開によってさらに2.5倍へと伸びる成果につながりました。
まとめ
デジタルマーケティングの成果は一度の施策で完結するものではなく、方針整理を軸に現状分析と改善を重ねることで最適化が進んでいきます。今回紹介した事例も、目的の明確化やデータ活用を通じて継続的な成長を実現した好例です。自社に当てはめる際は、課題を正しく把握し、優先順位をつけて取り組むことが大切です。
アクトデザインラボでは、戦略設計から施策実行、改善のサイクルまで一貫して支援し、企業が長期的に成果を積み重ねられるよう伴走しています。「施策を実行しても成果につながらない」「改善に時間と労力ばかりがかかってしまう」といったお悩みがあれば、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。