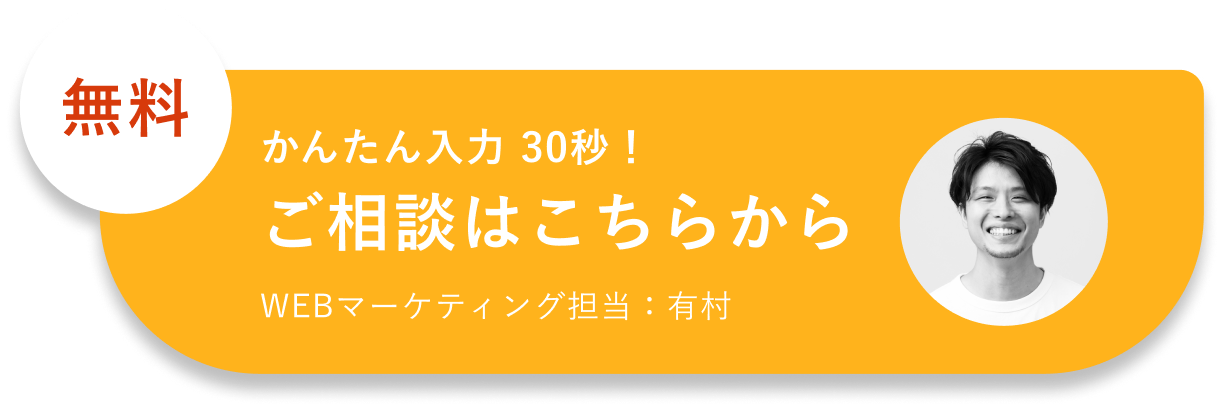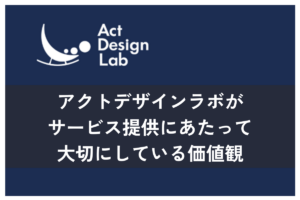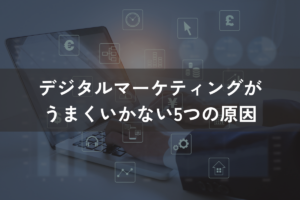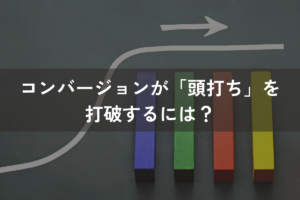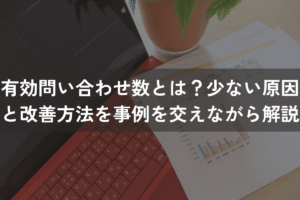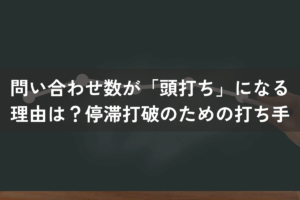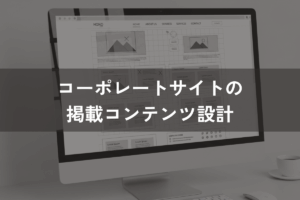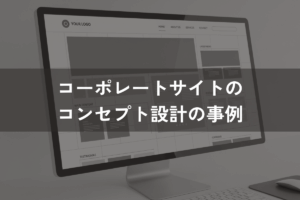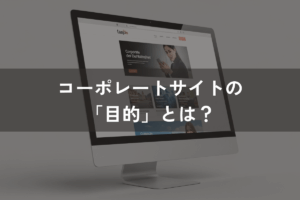Webサイトのコンバージョンを上げるにはどうすれば良いのかは、多くのWebマーケティング担当者が頭を悩ませる問題です。どんなに素晴らしい商品やサービスも、ユーザーの手に届かなければ意味がありません。コンバージョンの有無は自社の売上にとって死活問題といえるでしょう。
「コンバージョンの改善」というと、一見難しく思われがちです。しかし、6つのポイントを押さえて改善していけば、コンバージョン数を着実に伸ばすことが可能です。
これから紹介する方法は、どんな業種や業態でも共通して活用できる内容です。またコンバージョンの基礎からお伝えするので、Webマーケティングの知識が少なくても問題ありません。自社サイトのコンバージョンを上げたいとお考えの方は、当記事で紹介する方法を試してみてください。
コンバージョンとは
Webマーケティングにおけるコンバージョンとは、Webサイトに訪れたユーザーが目標とする行動を起こしたことを指します。ECサイトであれば商品の購入がコンバージョン、企業ホームページの資料請求やお問い合わせ、SNSのフォローもコンバージョンです。
コンバージョンの具体例は次のとおりです。
- ECサイトで商品が購入される
- Webサイトでサービスの申し込みがある
- 企業ホームページから資料請求や問い合わせがある
- Web広告からメルマガやLINEに登録される
- X(Twitter)やInstagramでフォローされる
このように、コンバージョンは媒体や目的で意味合いが異なります。共通するのは、Webサイト上で適切なゴール(コンバージョン)を設定し、ゴールに到達する戦略を練ることです。そして、ゴールに到達したユーザー数を測定することが、Webマーケティングにおいて非常に重要です。
コンバージョン率(CVR)とは
コンバージョン率(CVR:Conversion Rate)とは、Webサイトでコンバージョンが発生した割合を示す指標です。「訪問数」と「コンバージョン数」をもとに計算できます。
- コンバージョン率(CVR)= コンバージョン数(CV数) ÷ 訪問数(セッション数)× 100%
たとえば、ECサイトに100人のユーザーが訪れ、5人が商品を購入した場合、CVRは5%ということです。また、CVRを計算することで、コンバージョン改善の方向性が定まります。
例として、A社とB社のWebサイトの申し込み数を比較してみます。
| A社 | B社 | |
|---|---|---|
| 申し込み数 (コンバージョン数) | 60 | 30 |
| Webサイトの訪問数 (セッション数) | 1,200 | 400 |
| コンバージョン率 (CVR) | 5.0% | 7.5% |
コンバージョン数はA社の方が多いですが、コンバージョン率はB社が優れています。この場合、A社はコンバージョン率を改善し、B社はセッション数を増やせば良いと判断できるでしょう。
このように、CVRを計算すれば客観的に改善ポイントを分析できます。
コンバージョンを上げる6つのポイント
自社サイトのコンバージョンを上げるためには、次の6つのポイントを元に改善することが重要です。
- Webサイトのセッション数を増やす
- ターゲットを最適化する
- ユーザー導線を可視化する
- LP(ランディングページ)を改善する
- CTA(コール トゥ アクション)を改善する
- 商品やサービスを改善する
自社サイトの「コンバージョン数」「セッション数」「コンバージョン率」を測定したうえで、どのポイントを改善すべきか判断してください。
Webサイトのセッション数を増やす
コンバージョンを上げるもっとも単純な方法は、Webサイトのセッション数を増やすことです。
たとえば、セッション数が100でコンバージョン率が5%なら、コンバージョン数は5件となります。セッション数が2倍になれば、コンバージョンも10件に増えるでしょう。
- コンバージョン数=100件(セッション数)×5%(CVR)=5件
- コンバージョン数=200件(セッション数)×5%(CVR)=10件
母数を増やす単純明快な方法ですが、コンバージョン率の数値が高ければ効果的です。セッション数を増やすには、次の2つの方法があります。
- 自然検索から流入を増やす
- Web広告から流入を増やす
| 方法 | 施策の例 |
| 自然検索 | ・新規コンテンツを作成する ・既存コンテンツを改善する ・サイト全体を改善する ・SEO対策を実施する |
| Web広告 | ・SNS広告を出稿する ・リスティング広告を出稿する ・動画広告を出稿する |
自然検索は、成果が出るまで時間がかかります。検索キーワードの選定、記事などの良質なコンテンツの作成、SEO対策、コンテンツのリライトなども必要です。数ヶ月という長期目線でのサイト改善が必要ですが、中長期的に見ればユーザーの安定的な流入を見込むことができ、コンバージョンアップにつながるでしょう。
一方で、Web広告の場合は広告費を使えばすぐにセッション数を伸ばせます。しかし、ターゲティングを間違えたり、クリエイティブやLPのクオリティが低かったりするとコンバージョン率の低下につながるため注意が必要です。
ターゲットを最適化する
ターゲット設定を間違えていたり、ターゲットに合わないユーザーを集客したりしている場合、コンバージョン数は伸びません。少し極端かもしれませんが、下の例はターゲット設定がズレることはWebマーケティングで起こりがちなミスです。
- 20代女性に販売を考えていたが、実際に需要があるのは40代女性だった
- 20代女性向けサービスなのに、実際の訪問ユーザーは40代女性ばかり
リスティング広告の場合、年齢や性別に加え、キーワードの絞り込みが必要です。SNS広告の場合、オーディエンスやアフィニティ(興味関心)などの設定が可能です。メインターゲット以外のユーザーへ配信制限を行うことで、本当に届けたいユーザーへの露出が増えコンバージョンが増えることもあるでしょう。
ターゲットを最適化するには、「ペルソナ設定」と「キーワード選定」が重要です。
ペルソナとは、ターゲット像を明確にするため見込み客の人物像を設定することです。性別、年齢、居住地、職業、家族構成などを決め、コンバージョンを獲得しやすいユーザーを見つけます。
正しくペルソナ設定を行うことができれば、ユーザーがどういったキーワードで検索するのか、自ずと想定することができます。
ユーザー導線を可視化する
ユーザーのWebサイト訪問からコンバージョンまでの導線を可視化すると、コンバージョン改善のポイントを見つけることができます。
カスタマージャーニーを作成して分析すれば、ユーザーの行動が明らかになります。カスタマージャーニーとはユーザーが商品と出会い、申し込むまでの流れを可視化することです。ユーザー視点でサイト全体を見直せば、CVRが劇的に向上する可能性があります。
よくあるユーザー導線の問題には、次のようなものがあげられます。
- コンバージョン地点に到達するまでのページ遷移が多い
- LPへつながるリンクがわかりにくい
- ページの表示速度が遅い
- わかりにくい文言や表現がある
- 情報が古く信用性が低い
- スマートフォンのUIが見にくい
- サイト全体のユーザビリティが悪い
Webサイト内でユーザーがどのように動くかは、ユーザー視点に立たなければわかりません。たとえば、商品紹介ページを閲覧しているユーザーが、他社と比較検討するためにページを離脱するかもしれません。その場合、ページ内に他社との比較表を入れると離脱率が下がる可能性があります。
また、コンバージョンを狙ってLPを制作していても、LPとは関係のない場所からコンバージョンを獲得することもあるでしょう。コンバージョンを上げるためには、ユーザーが迷うことなく目的地に到達できるかを考え、離脱につながるポイントをいかに減らえしていくかが重要です。
LP(ランディングページ)を改善する
LPは、ユーザーがコンバージョンの前に到達する最終ページです。改善できれば大きな成果につながるでしょう。逆に、LPの質が低いと、ユーザーがLPに到達するまでの導線がどれだけ良くても、コンバージョンにつなげることはできません。具体的なLPの改善ポイントは次のとおりです。
- 魅力的なデザインになっている
- 読みやすい構成になっている
- ファーストビューでユーザーの注意を引ける
- ユーザーの注意を引くコピーがある
- ベネフィットを示している
- ストーリーを感じることができる
- 権威性や専門性を示している
- 誤解を招く表現は入っていない
- ユーザーの共感を得られる文章になっている
- ストレスなく読むことができる
- 口コミや感想が入っている
- 怪しさや胡散臭さがない
必ずすべてを満たす必要はありませんが、上記のポイントでLPの改善箇所があれば、修正を検討してみてください。
また、LPの執筆において「新PASONAの法則」など文章の法則を活用することも効果的です。
新PASONAの法則
- 潜在的な問題や悩みを明確化する(Problem)
- 悩みの共感や事例を紹介する(Affinity)
- 悩みに対する解決策を提示する(Solution)
- 商品やサービスを提案する(Offer)
- 期間や対象を絞り込む(Narrow down)
- いますぐ行動を呼びかける(Action)
LPを読んだユーザーが商品やサービスを得ることで、自身の問題が解決し理想の状態に近づくことができると訴求できれば、コンバージョンは間違いなく上がっていくでしょう。
CTA(コール・トゥ・アクション)を改善する
CTAの改善もコンバージョンを上げるうえで大きな影響を与えます。CTAは商品の購入ボタンや資料請求のお申し込みフォーム、お問い合わせ電話番号などのことです。
フォームやボタンなんてどうでも良いと放置しがちですが、CTAを改善するだけでコンバージョン率が大きく改善するケースは多くあります。CTAの改善ポイントは次のとおりです。
- CTAの数を増やす
- CTAの設置場所を変更する
- サイズや色を変更する
- マイクロコピーの文章を変える
- 心理抵抗を感じないか確認する
- フォーム入力が面倒ではないか
CTAの数、場所、サイズ、色といったデザイン面を見直すことは重要です。
ただし、コンバージョン数の改善において特に重要なのは、ユーザーの心理抵抗を減らすことです。たとえば、購入手順が面倒だったり、個人情報の入力項目が多かったりすると心理的なハードルが高くなり、離脱されてしまいます。
また、コンバージョン数を増やしたいがために、CTAを複数設置してユーザーの混乱を招いてしまうことにも気をつけてください。CTAの設置場所は「コンテンツ最上部」「コンテンツ最下部」「精読率の高い中間地点」「サイドバー」がおすすめです。
ユーザー視点に立ってスムーズにコンバージョンにつながるCTAを作れば、コンバージョンは上がっていくでしょう。
商品やサービス、コンテンツを改善する
「セッション数」「ターゲティング」「ユーザー導線」「LP」「CTA」など、Webマーケティングに問題がない場合、商品やサービス、コンテンツに改善が必要な可能性があります。いかにマーケティングが優れていても、ユーザーがコンテンツに価値を感じなければコンバージョンの獲得はできないからです。
商品やサービスを改善するうえでやるべきことは「3C(スリーシー)分析」です。「自社(Company)」「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」に分けて分析するフレームワークで、頭文字の「C」を取ったものです。
| 項目 | 分析内容の例 |
| 自社(Company) | ・自社の強みと弱み ・ブランドイメージ ・市場シェア |
| 顧客(Customer) | ・ユーザーのニーズ ・市場規模や動向 |
| 競合(Competitor) | ・競合他社の強みと弱み ・競合他社の評価 |
3C分析を実施することで、顧客のニーズに応え、競合他社に負けることのない商品やサービスを作りあげるヒントが見つかります。
また、自社サイトの記事などのコンテンツも、ユーザーの利益を考えて作成することが大切です。わかりやすく見やすいコンテンツであれば、滞在時間やリピート率が増え、検索エンジンからの評価も高まります。コンテンツが高品質であれば、自然と検索順位が上がり、コンバージョンも増えていくでしょう。
コンバージョンが低下すると集客方法ばかりに意識が向いてしまいがちですが、商品、サービス、コンテンツの見直しも忘れないようにしてください。
当社が実施したクライアント様のコンバージョン改善事例
当社アクトデザインラボ株式会社では、あらゆる業種や業界の企業様のWebマーケティングを支援しています。販売する商品やサービス、集客方法はクライアントによって異なるため、それぞれに合ったコンバージョン改善施策をカスタマイズすることが重要です。
当社の支援によってコンバージョンが改善した事例を3つ紹介するので、ぜひ自社のマーケティングに照らし合わせてみてください。
電材業界A社様【CV数10件/月→30件/月に増加】
| 業界 | 電気設備資材 |
| 施策内容 | リスティング広告、SEO対策、ディスプレイ広告、サイト改善 |
| ポイント | 会社情報の記載、コーポレートサイトへの導線設計、フリーダイヤルの追加 |
電材業界のA社様はターゲットが法人企業であるため、一つひとつの顧客から信頼を得ることが重要でした。そのため、顧客対応の方と定例会で話し合いを重ね、「顧客がなぜ相談してくるのか」「事前にどのような情報収集を行っているのか」「社内上申に必要な情報はなにか」など、徹底的に顧客を理解することに専念しました。
その結果、顧客とのコミュニケーション設計、コーポレートサイトへの導線の調整、訴求軸の改善、フリーダイヤルの取得を実施し、コンバージョン数が月10件から3倍の30件まで増加することに成功しています。
中古品買取業界B社様【CV数30件/月→50件/月に増加】
| 業界 | 中古品買取 |
| 施策内容 | リスティング広告、SNS広告、サイト改善 |
| ポイント | コールトラッキングツールの導入、有効な問合せデータをもとにした広告配信とLPの最適化 |
中古品買取業界のB社様の場合、すでに電話による問い合わせでコンバージョンにつながる事例がありました。そのため、コールトラッキングツールを活用し、電話での問い合わせ履歴をもとに顧客の情報の分析を実施しました。また、電話の問い合わせの内容を精査したことで、顧客の属性やニーズを把握し、情報を元にリスティング広告、SNS広告を最適化することができました。
電話とWeb広告を最適化することで、コンバージョン数は月30件から50件に増加しています。
物流・ロジスティクス業界C社様【CV数30件/月→80件/月に増加】
| 業界 | 物流・ロジスティクス |
| 施策内容 | リスティング広告、SNS広告、サイト改善、導線設計 |
| ポイント | コンバージョンポイントの新設と調整、ターゲットキーワードの精査 |
物流・ロジスティクス業界C社のコンバージョン改善のポイントは、LPの改善とコンバージョン定義を再設計することにありました。顧客に魅力を感じてもらうため、クライアントが保有しているデータをどこまで新規顧客へ提案できるかを調整し、顧客のニーズに合った訴求軸でLPを改善しました。
加えてコンバージョンポイントを設計し直すことにより、月30件から80件と大幅にコンバージョンを改善することに成功しています。
コンバージョンが下がってしまう理由
「今まで問題なくコンバージョンを獲得していた」「コンバージョンの改善をしている」という場合でも、外的要因によってコンバージョンが下がってしまうケースがあります。主なコンバージョン低下の理由は次の2点です。それぞれの理由の原因や特徴を解説します。
- 競合他社の影響
- ユーザーのニーズや市場の変化
競合他社の影響
コンバージョンが下がってしまう理由の一つに、競合他社の影響が考えられます。
競合他社が増加することや、他社が独自の強みを活かしたサービスや、魅力的なキャンペーンを提供すれば、相対的に自社の価値が下がってしまう可能性があります。また、競合他社のサイトが検索で上位表示したり、リスティング広告の入札を強化したりしている場合も、コンバージョン低下につながってしまいます。
競合他社の影響でコンバージョンを下げないためには、他社と訴求ポイントをずらしてユーザーにアプローチしたり、他社のアイデアをもとに新たな価値を見出したりすることが必要です。競合他社のマーケティング手法、コンテンツ内容、検索順位などを分析していきましょう。
そのうえで集客方法を改善したり、集客経路を増やしたりすることを検討してみてください。また、リスクはありますがターゲットを変更したり、新たな市場を開拓したりすることも一つの手です。
何より重要なのは、競合他社に真似することのできない独自の強みを見つけて差別化することです。「あなたの会社はどこが優れていますか?」「他社と比べて何が違うのですか?」この質問に答えられる個性や強みがあれば、競合他社に埋もれることはなくなります。
ユーザーや市場の変化
ユーザーのニーズや市場は日々変化しており、適応できなければコンバージョンは下がっていきます。去年の同時期は好調だったのに、今年はまったくコンバージョンを獲得できないという状況であれば、この1年で市場にどのような変化が起きたのか見極める必要があります。
たとえば、近年ではChatGPTなどのAI(人口知能)の出現や、世界的なSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みが生まれました。新型コロナウイルス発生以後も変わらず景気は改善しておらず、ユーザーがより安い商品やサービスを求めて流れていってしまうことも考えられます。
また、WebマーケティングにおいてもGoogleの検索エンジンのアルゴリズム変更や、SNSのルール改正も考えられます。Googleのアルゴリズムアップデートによって、突然コンバージョンが激減することも珍しい話ではありません。
ユーザーや市場の変化に惑わされずコンバージョンを獲得し続けるには、常に世の中の動向を分析し、小さな変化にも敏感になることです。どんな変化があっても原因さえ特定できれば対処することができるはずです。
コンバージョンを上げるにはPDCAを回し続けること
当記事では、6つのコンバージョンを上げるポイントをお伝えしましたが、もっとも重要なことはPDCAサイクルを回し続けることです。
コンバージョンを上げるための施策で、Plan(計画の立案)→Do(計画の実行)→Check(実行した計画の評価)→Action(問題点の改善)というサイクルを繰り返し、課題を見つけて改善していきます。
コンバージョン率を計算することもPDCAサイクルの一貫です。セッション数やコンバージョン数を把握することで、コンバージョン低下の原因を探ることができます。そして改善施策を打ち、優先順位を付けながら実行していけば、確実に状況を良くしていけるでしょう。
コンバージョンの分析のためGoogleアナリティクスやヒートマップツールを利用するのも効果的です。そういったツールを利用して定期的なチェック体制を作れば変化が起きたときに素早く対応できます。
このようにコンバージョンを上げるには、長期的な視点でPDCAサイクルを回していくことが重要です。自社の売上に直結する重要なプロセスですので、辛抱強く改善し続けてみてください。
コンバージョン改善は専門家に任せることがおすすめ
ここまで、コンバージョンやコンバージョン率とはどういったものか、コンバージョンを上げるにはどうすれば良いのか解説しました。業界や業態を問わず共通する6つの改善ポイントを実践すれば、着実にコンバージョン数は上がっていくことでしょう。
しかし、前述したとおりコンバージョンを上げるにはPDCAサイクルを回しながら、長期的な視点で対応していく必要があり、社内のWeb担当者のみで進めるには荷が重いものです。そのため、本腰を入れてコンバージョン改善を図るのであれば、Webマーケティングの専門家に相談することがおすすめです。
専門家の目があれば、自分たちでは気付かない集客のボトルネックを見つけだし、具体的な解決策を立てることが可能でしょう。Webサイトの改善はもちろん、リスティング広告、SNS広告、SEO対策など、多くのWebマーケティング手法を用いた多角的な対応もできます。
当社アクトデザインラボ株式会社では、お客様とコミュニケーションを取りながら、課題を浮き彫りにし、企画・設計〜開発運用までワンストップで支援させていただいています。「コンバージョン改善に取り組んだものの成果が上がらない」「時間と労力だけが無駄になってしまった」そんな事態に陥らないためにも、ぜひ一度当社にお気軽にお問い合わせください。